これまでの記事はこちら
写真という生の寄す処
台北の独立系書肆・書店「田園城市」はお気に入りの本屋だ。2024年11月、台北に住みはじめてすぐ、旧知の店主・陳炳槮(ヴィンセント・チェン)に会いに、降り続く雨のなか店を訪ねた。1994年にこの出版社と書店をたちあげて30年。コロナ禍で久しく会えていなかったにもかかわらず、少し痩せて小さくなったヴィンセントはあいかわらずの柔らかい笑顔で迎えてくれた。
ここには、台北のどの書店ともちがう独特の選書のセンスがある。棚に並んだ本と本が、となり同士の思いがけない出逢いの歓びに静かに沸き立っている。判型、デザインともに個性的で美しいアート、写真、建築、都市にかかわる選りすぐりの書物たち。絞り込まれたジャンルの良書を、読むべき人に確実に届けたい、という真摯で誠実な思いがこの小空間を満たしている。内容に妥協することはないが、本のオブジェとしての存在感をなにより大事にしていることも「田園城市」の特徴だろうか。付設の地下ギャラリーでは新進の静物写真家の個展が開かれていた。
ヴィンセントとしばらく談笑したあと、書棚から新装なったばかりのロラン・バルト『明室』(台北:時報文化、2024)を抜きだし、買い求める。原著は “La chambre claire”、邦訳では『明るい部屋』である。
この本には特別の思いがある。バルトがパリで交通事故のあとすぐに亡くなった1980年3月末、パリにいた私はバルトがもういないという深い喪失感を抱えてベルギーに逃げるように飛び出し、ブリュッセルのとある書店で出たばかりの遺著『明るい部屋』を手にとった。この銀色の本は私に、一人の敬愛する思想家の「生」そのものの帰結を痛いほど鮮やかに示した。いや、著者ですら想定しなかったであろう「帰結」のなかに、その人の思索的生涯のすべてが凝縮されているという、哀しいほどの真実を。そして、そんな生の「寄す処(よすが)」としての遺著が、「写真」という、人間の記憶の特権的な媒体をめぐる逡巡に充ちた手記として出現したことに、私はとりわけ心打たれた。写真というメディアが、私のなかで思索のためのもっとも重要な手がかりとして意識されたのも、この時からだったろうか。そしていま、44年後の台北で、私はふたたびこの本を手にしている。表紙に掲げられた、子犬を抱いた少年の、永遠を見つめるような眼差しに捕えられながら……。私の目は、おのずから自分自身の内奥に折り重なって整序されぬままに堆積する記憶の層へと、ゆっくり浸透していく。


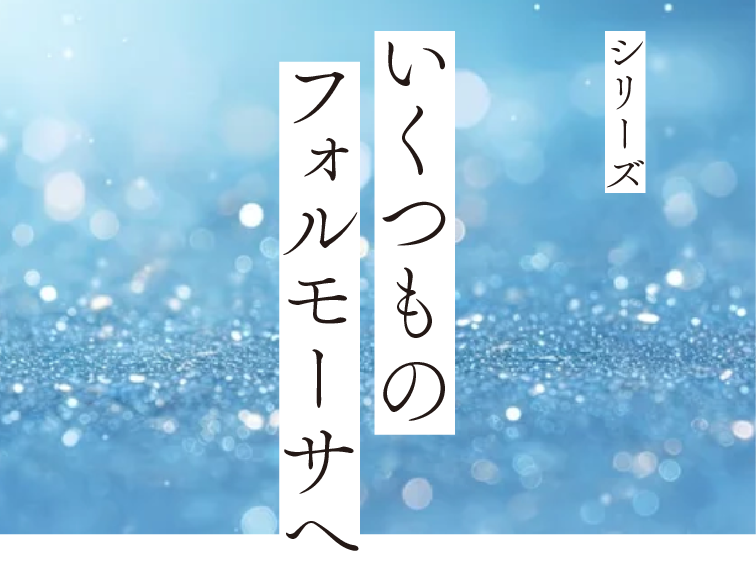





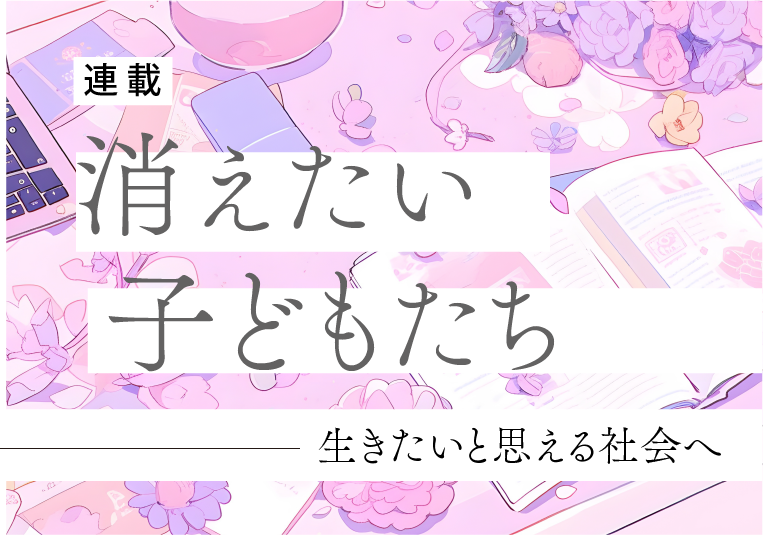
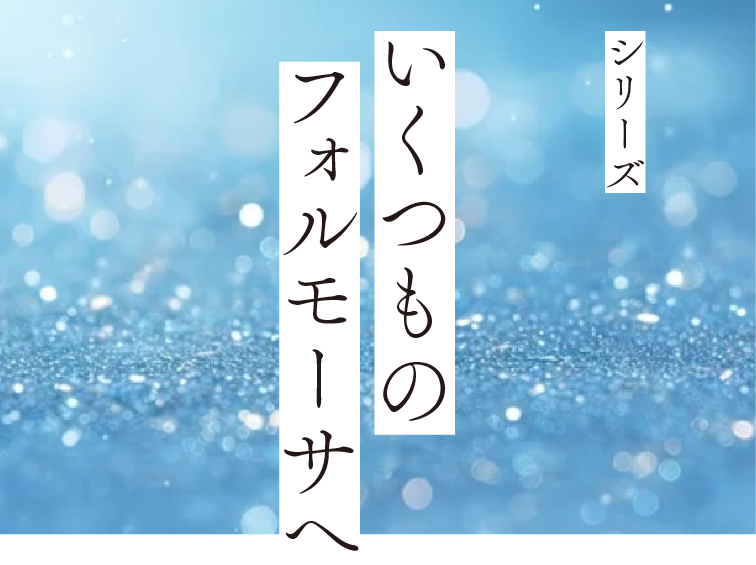
.jpg)

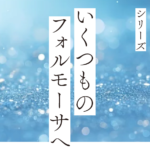

-150x150.jpg)