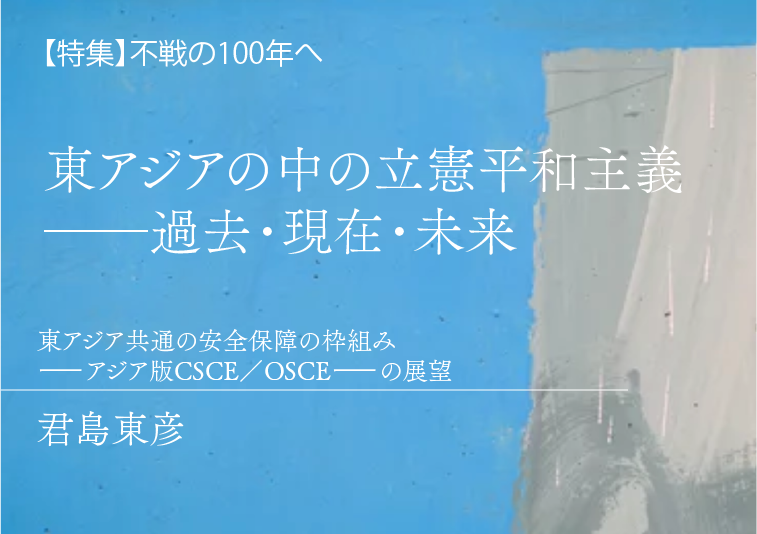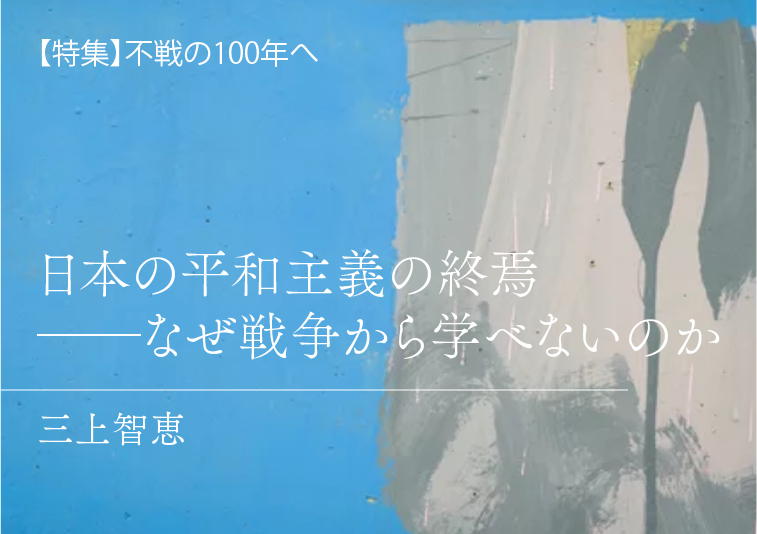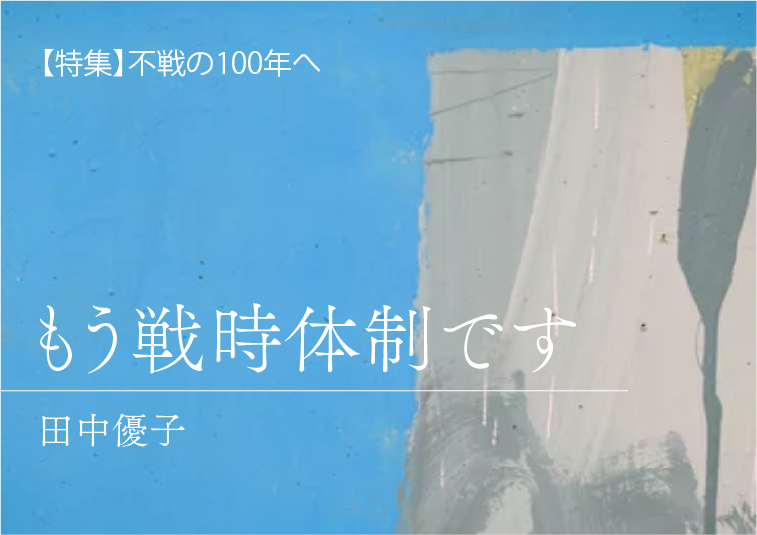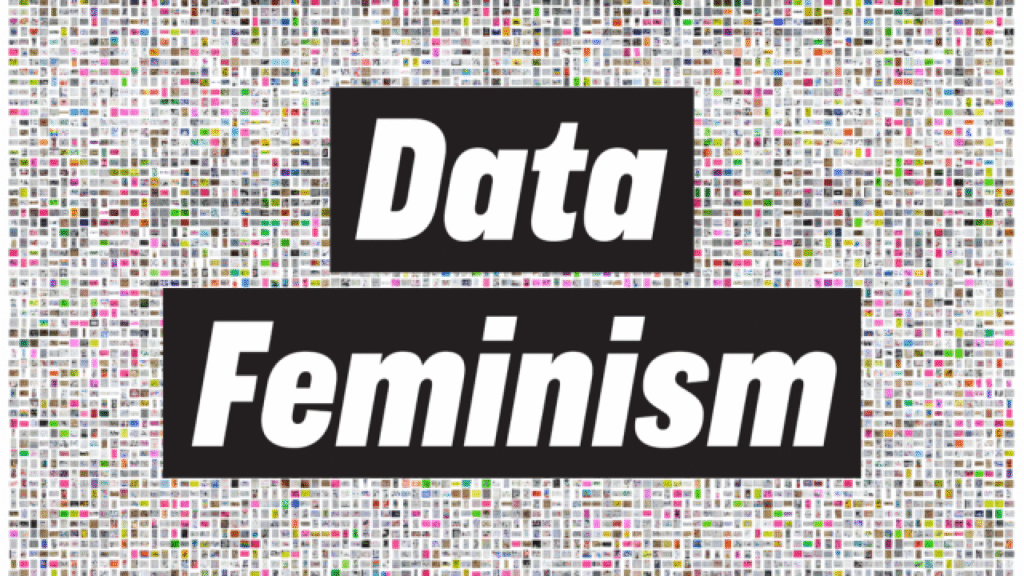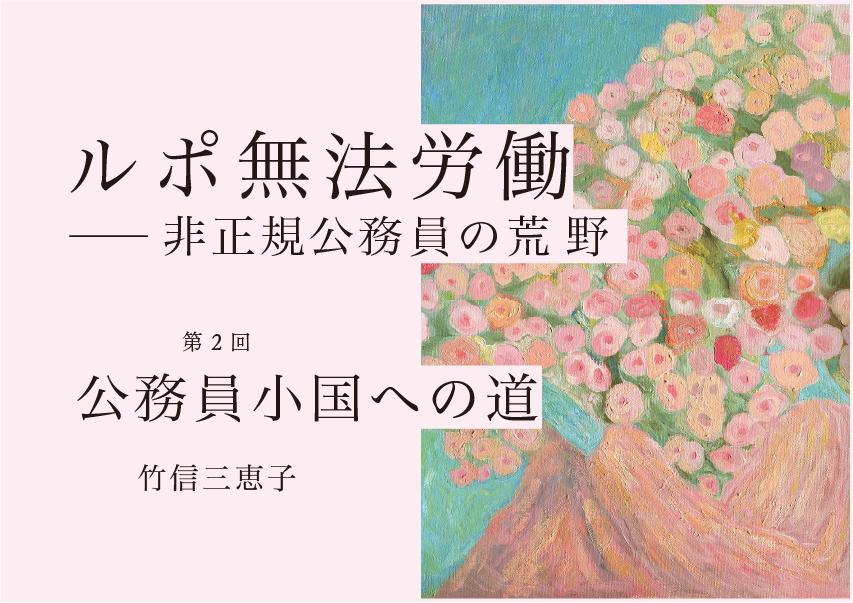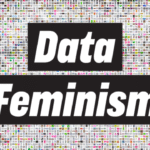ポツダム宣言の受諾によって大日本帝国が崩壊して80年が経った。この大きな節目にあたって、日本の立憲平和主義の俯瞰的な議論、根源的なとらえ直しを試みたい。
安保法制成立から10年、安保3文書改定から3年が経過した現在、日本の立憲平和主義の現状をどう見たらよいだろうか。中国外交が欧米列強および日本に圧迫された「屈辱の近代」を乗り越えようとする側面を強く表現する中で、日米は軍事的抑止力強化で対応しようとしている。そのため日本の立憲平和主義は後退を余儀なくされている。いま日本の立憲平和主義の活路はどこにあるのだろうか。
平和論は関係論である
日本の立憲平和主義をとらえ直すにあたって、本稿はカント『永遠平和のために』の一節から始めたい。この本の冒頭でカントは平和を定義している。「平和とは(国家間の)一切の敵対関係を終わらせることである」(君島による意訳)。つまり、平和とは関係性の概念であるということである。
平和にはつねに相手がいる。平和は一国で考えることも一国でつくることもできない。国家の武装、軍備は相手に対する恐怖、不信感の表現である。相手に対する不信感を減らさなければ軍縮はできない。軍事化を抑制するためには、軍事の話だけではなく、軍備の基底にある敵対関係の克服の議論をしなければならないのである。相互の不信感を減らすのは、軍備ではなくて、関係構築、外交である。平和論は軍事論ではなくて関係論である。
9条は日本の安全保障の規定ではない
日本の立憲平和主義は1946年日本国憲法の前文と9条に立脚している。これらは不可分のセットである。われわれは前文と9条をつねにセットで読まなければいけない。9条のエッセンスは軍事的主権の自己制約である。9条は国家の自衛権行使に依存しない国際関係、国際秩序を想定していた。そして9条は日本の安全保障の規定ではない。前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」という部分が日本国憲法の安全保障構想である。この部分が「非武装日本の安全は国連の安全保障システムによる」ということを意味していたことは疑う余地がない。しかし冷戦ゆえに国連の安全保障システムは実現せず、日本政府は1951年の二つの条約(西側連合国との講和条約、日米安保条約)によって、西側同盟の一員となることで日本の安全を追求する方向性を選択した。
9条は日本の安全保障の規定ではなくて、日本帝国主義の被害を受けた人々の安全保障の規定であるというべきであろう。このことは1946年3月7日、前日に日本政府が発表した日本国憲法の最初の「草案要綱」を新聞紙上で読んだ日高六郎1が、後に回想した文章で書いているとおりである。日高はこう書いている2。
……私は、アジア全域の戦禍と虐殺を経験した民衆が、どのように日本国憲法を読み、第9条を理解するであろうかを考えた。彼らにとっては、第9条は、日本が再度、残虐な武力行使、独善的な政治行動、人権侵害の差別行為をしないことの国際的な保障でなければならなかったはずである。……第9条に懲罰的意味がふくめられていることは、彼らにとっては当然のことであった。……私たちにとって不可欠ないとなみは、十5年戦争を思い出し、記憶にきざみつけること。歴史として残すこと。反省の感情と人間としての倫理感を結びつけること。そのことができないで、「第9条」の世界的先駆性を語るのは、恥ずかしい……。
わたしは日高のこの認識に共感する。アジア太平洋戦争における日本の被害ではなくて日本の加害が9条をもたらしたのである。日本の立憲平和主義は東アジアにおける敵対関係の克服を目的として(いわば国際的な誓約として)成立し、現在においてもそのような意義を持っているとわたしは考える。