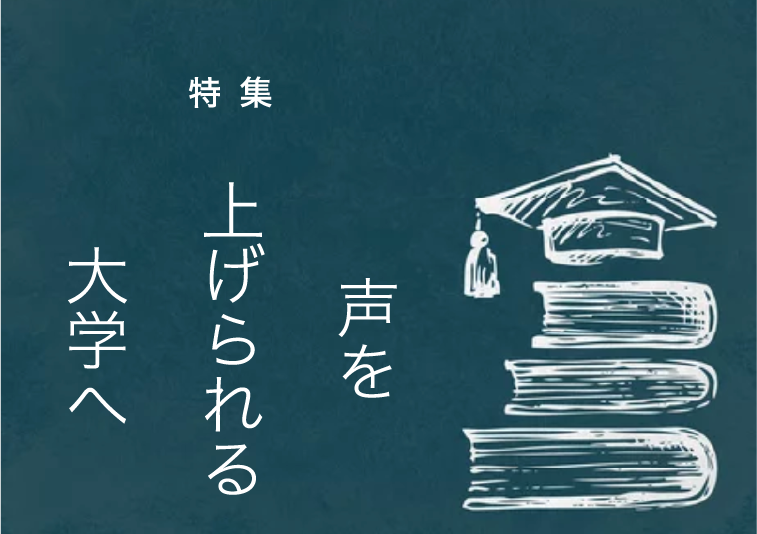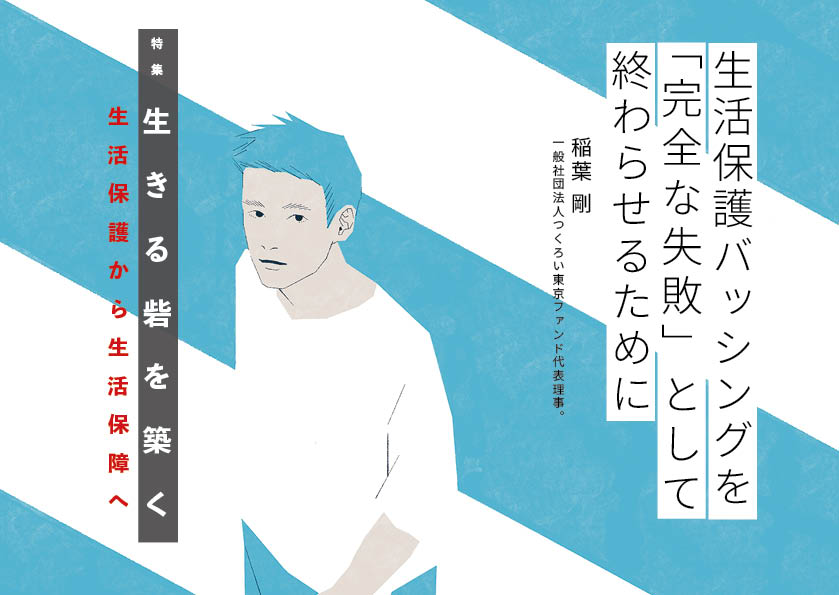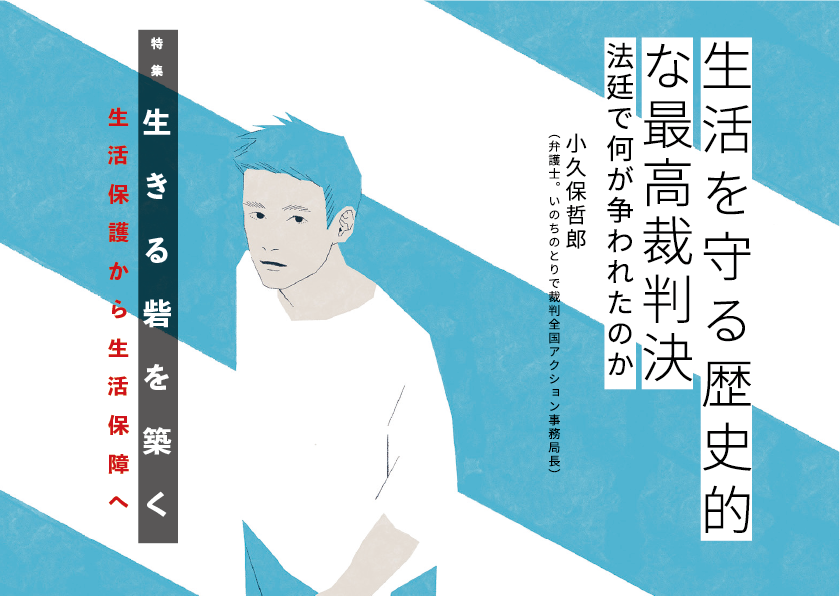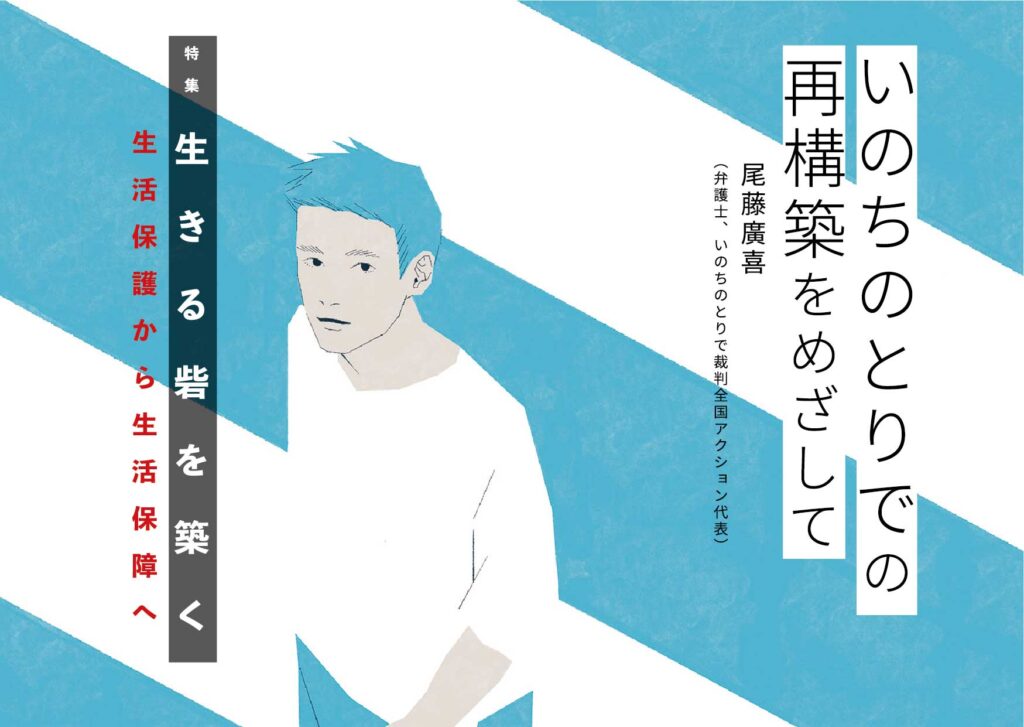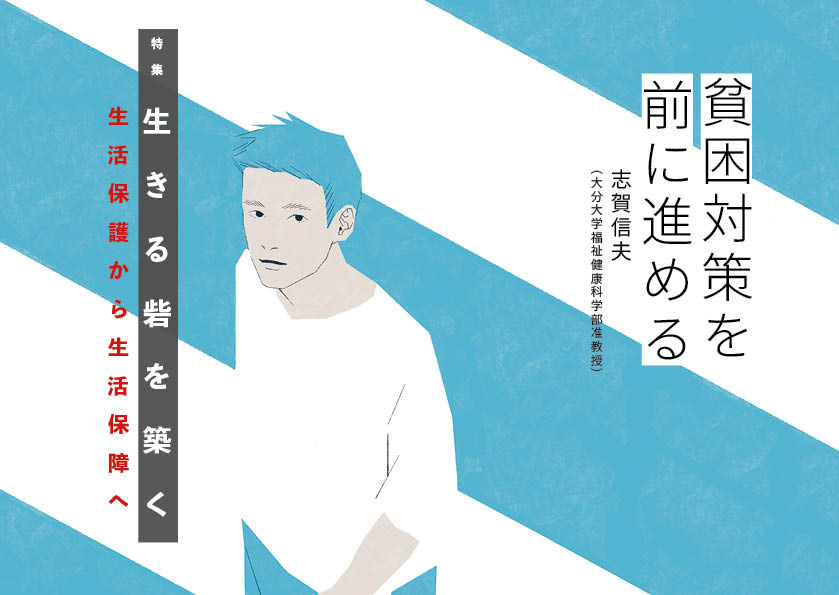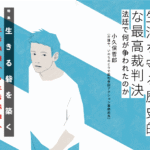「なんでも相談会」
2020年4月、コロナ感染症の拡大を受け、弁護士、司法書士、市民団体および労働組合等が実行委員会を作り、電話による全国的な「いのちと暮らしを守るなんでも相談会」を3年間、実施してきた。相談会は17回開催し、1万5125件の相談に応じ、コロナ禍でのセイフティーネットとしての役割を一定果たした。
2023年以降は電話相談だけでなく、対面相談、食料支援も加え、相談会を実施してきた。また、一部では「ボイチャ相談」としてインターネット回線を利用した相談も開始した。筆者は2023年以降、相談会の実行委員長を務めている。
2023年1月から2024年7月までの6回の相談会には3965件の相談が寄せられている。食料支援も1594件となって、多くの相談者が食料支援も受けた。食料支援は一部の相談場所に限られていることを考えると、食料支援のニーズは極めて高くなっていると言える。
相談者は60代、70代以上が全体の約6割を占める。無職者からの相談が59.3%を占め、他方、正規労働者5.4%、非正規労働者12.3%であり、有職者の中では非正規労働者からの相談が多くなっている。
相談内容別では生活費に関する相談が約40%、そのうち生活保護受給者14.2%、受給申請中未受給は10%となっている。健康問題7.1%、債務問題7.0%、労働問題(被用者)6.5%と続く。
食料支援にともなって多くの相談が寄せられている。特に目を引くのは、生活保護を受給中の方が食料支援を求めて相談されていることだ。2024年8月27日の相談では、生活保護利用中の40代男性単身者が、「たばこもやめて節約しているが、生活が苦しく所持金もわずか、死にたい」という声を寄せた。また、エアコンが設置された世帯でも、現在の物価高のもとで、「電気代の支払いをさけるためエアコンをつけていない」など、生命に関わる相談が少なくない。
こうした事態が起きている原因は、人の尊厳を踏みにじる違法な生活保護基準の引き下げと、昨今の異常な物価高騰である。生活保護制度が最低生活を支え切れていない現実がある。
経済・生活苦による自殺者の増加
日本は2020年を100として2023年の平均の消費者物価指数は105.9となり、生鮮食料品を除く食料品は7.5%上昇と、オイルショック後の1975年以来の異常な物価高騰となっている。2024年も111.2と、2024年以降もこの流れが続いている。この物価高騰が貧困者を痛めつけている。
日本の自殺者総数は、最大だった2003年の3万4427件から下がっており、ここ数年は2万1000件台で推移している。2023年は2万1837人、2024年の速報値は2万268人であるものの、注目すべきは、経済・生活苦による自殺者が2022年、23年と急増し、23年は5100件と21年の1.5倍となっていることである。
さらに、生活保護受給者の自殺は2022年に1014人、2023年1071人であり、生活保護受給者の自殺率は、全人口の場合と比較して3倍に達している。
さらに、2023年の生活保護受給者の自殺者のうち118名が生活苦によるもので、これは2022年に比べて実に37.2%もの増加となっている。生活保護を受給しているにもかかわらず、生活苦による自殺が急増している実態がある。この事態は、生活保護制度がその機能を果たしていないことを如実に物語っている。
生活保護制度によっても最低限度の生活が営めないということは、日本における基本的人権の保障システムの崩壊といってよい。そんなことがあっていいのか。現在、生活保護基準切り下げの違法性を訴えて全国で取り組まれている「いのちのとりで裁判」では、司法における正義・公平が問われている。
【関連】「正念場を迎える「いのちのとりで」裁判」尾藤葊喜