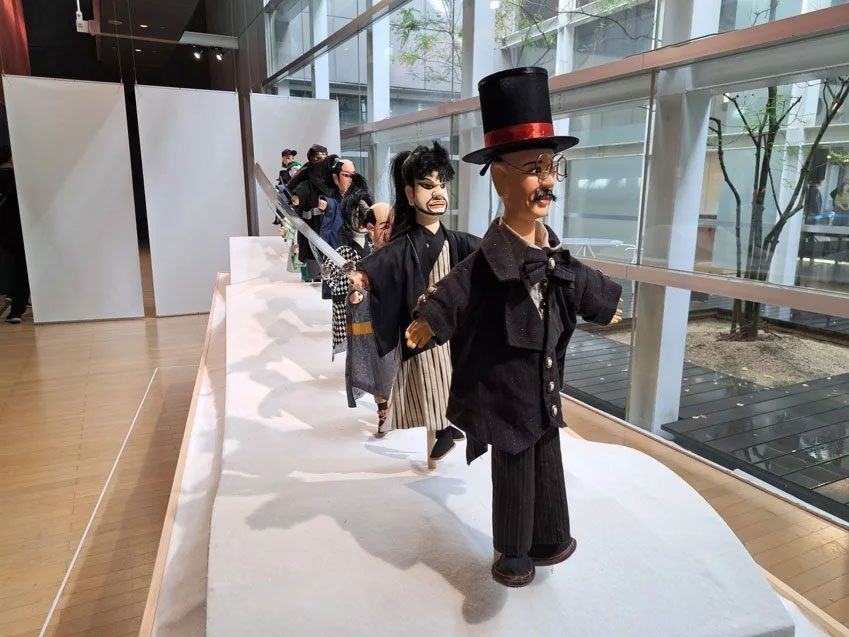〈移行期正義(Transitional Justice)〉……過去に大きな不正や人権侵害があった社会が、真実を追求して責任の所在を明確にすると共に、分断された社会の和解をめざし、より良い未来を築くために行なうプロセスのこと。
これまでの記事はこちら(連載:台湾・麗しの島〈ふぉるもさ〉だより)
今年6月、映画『福田村事件』が台北映画祭で上映されるというので、来台した映画監督の森達也さんに《移行期正義》の話をした。個人的に「これは日本の現代における《移行期正義》映画だ」と感動したからだ。福田村事件とは1923年9月6日、関東大震災における朝鮮人虐殺の余波で高知県から来た薬売りの行商一行9名が殺された史実で、映画は昨年、関東大震災から100年の節目に製作された。森監督はこの《移行期正義》という概念に共感を込めてフムフムと聞いてくださったが、
「でも〝正義〟という言葉が好きじゃないので、そこに引っ掛かりますね」
と言われ、たしかにと思った。なるほど〝正義〟といわれると胡散くさい感じがするし、たぶん多くの日本人は苦手な言葉だと思う。今どきの〝カワイイは正義〟とか〝おいしいは正義〟といった言い回しも、意味の不確定さを逆手に取ればこその言葉遊びといえそうだ。
移行期正義(Transitional Justice)とは、過去に大きな不正や人権侵害があった社会が、分断された社会の和解をめざし、より良い未来を築くために行なうプロセスをいう。多くの国々が独裁政権や軍事政権から民主主義へ移行した80年代から90年代にかけて生まれた言葉だが、台湾においても、戒厳令時代や白色テロの被害者に対する正義を実現するための取り組みがさまざまな分野で行なわれてきた。日本にとっても大切な考え方と思うが、なかなか広まらない言葉でもある。それは「日本はすでに〝清算〟を済ませたから関係ない概念」と考える人が多いからだと思ってきたが、もうひとつ、この「正義」という言葉への不信感もあるのかもしれない。
その感情のもとを遡れば、オセロの大逆転のように価値観が裏返った「大東亜戦争」にたどり着くのかもしれない。しかし一方で、その総括は終わっていない。今年の「終戦記念日」にことさら感じたのは、「敗戦」した自らの歴史経験を「終戦」というどこか他人事な言葉で覆い隠している不自然な現状である。しかし実は、日本人は戦後当初から、そんな風に「敗北」から目を背けようとしていたわけではなかった。