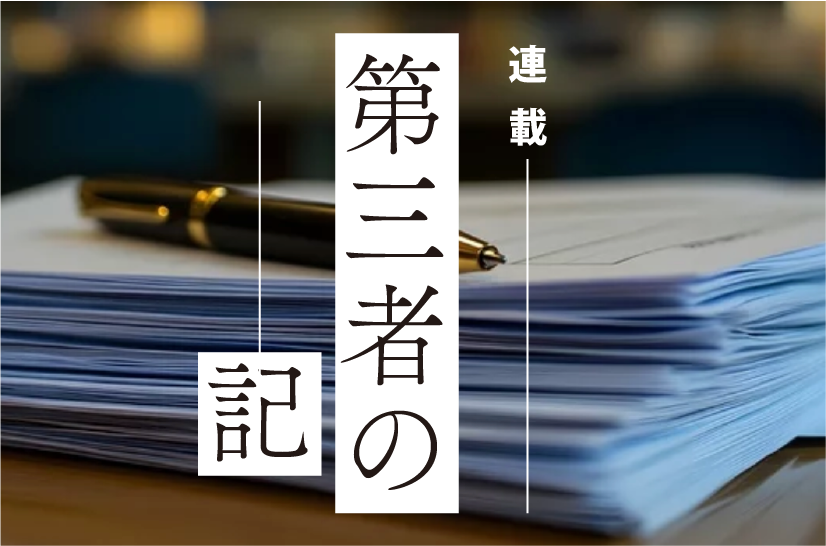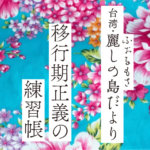県単位で失われる販売網
7月17日、毎日新聞社が「富山県内での新聞配送を9月末で休止する」と発表した。理由は印刷、輸送などのコスト増大だとしている。
これまで全国紙として47都道府県の読者に新聞を届けてきたが、10月から富山県内において新聞配達はされず、毎日新聞社の販売網は全国紙体制ではなくなる。一県のこととは言え、明治時代から全国紙の看板を掲げて販路を拡大してきただけに、その歴史にピリオドを打つのは苦渋の決断だったはずだ。
毎日新聞社のウェブサイトによると、富山県での新聞発行部数は840部。人口約100万人の県でこの部数はマスメディアと呼べるものではなく、毎日新聞の県別発行部数の中でも沖縄県(約220部)を除いて最低だ。
もともと富山県は「新聞激戦区」と言われ、地元紙の北日本新聞のほか、隣の石川県の県紙(地元紙)である北國新聞系統の富山新聞、中日新聞系統の北陸中日新聞が発行されている。県紙とブロック紙が3つもあるのに加え、全国紙では読売新聞が「中興の祖」の正力松太郎の出身地ということもあり、部数にこだわりが強く、営業に力を入れてきた。
毎日新聞社の元販売局社員は「富山県からの撤退は遅すぎたぐらい。他の新聞社と共同輸送するなど、経費を抑える工夫はしていたが、部数が少なすぎてコスト削減にも限界がある。昨今の輸送費、印刷費の上昇に見舞われる前から、利益を出すのは難しかった。全国紙体制の維持にこだわりズルズルと販売を続けてきたのが実態だ」と明かす。「販売競争でまともに戦えなかった結果が今の部数。もう何年も前から富山県内に毎日新聞の専売店はなく、わずかな部数を他系統の販売店に委託していた」。
専売店とは特定の新聞社とその社の発行する新聞だけを配達、販売する契約を結んでいる販売店のことで、日本の新聞社は明治時代から自社の専売店を増やすことで成長してきた。専売店は系列の新聞社から新聞を買い取って配達し、毎月の集金だけでなく、新しい読者を獲得する営業活動も行なう。
かつて「拡張団」と呼ばれたセールスチームが戸別訪問をするのは新聞業界独特の営業形態だったが、新聞社と専売店はこの経費を分担していた。新聞の「増紙」への取り組みは新聞社と専売店の二人三脚であり、インターネットの勃興で「新聞離れ」が社会現象になるまでは、多くの部数を持つ強い専売店を育てることが新聞社販売局の仕事だった。だが、今や全国紙、地方紙を問わず専売店の数は減少を続けており、高齢化などで店主が引退する専売店の後継者が見つからない事態も起こっている。「専売店網の維持」が「部数の維持」とされてきたが、そのバランスが崩れた。どう頑張っても減少の傾向を止めることは難しく、ついに新聞社は「販売網の縮小」に舵を切らざるを得なくなったといえよう。