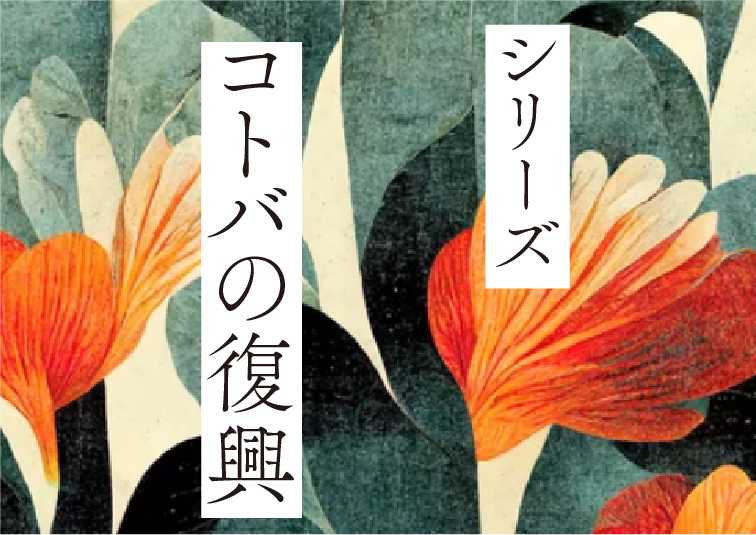国際世論となった「即時停戦」
ガザへのイスラエルの全面侵攻、市民への無差別殺戮が開始されてから8カ月近くが経つ。破局的事態の進行は止まらず、ガザは極限状態に陥っているが、注目すべき現象があるとすれば、それは「国際社会」の姿勢の変化だろう。
昨年10月に――直接的にはハマース(イスラーム抵抗運動)を中心とする勢力による奇襲攻撃を発端に――今回の危機が始まった時、世界は「テロとのたたかい」を掲げるイスラエルの行動を支持するかに見えた。事実、米国をはじめとする先進諸国政府は戦争だけが問題解決の道だとするネタニヤフ政権の主張を当初は全面的に支持、イスラエルと共に立つ姿勢を強調し、バイデン政権は大規模軍事支援・武器供与を開始するとともに、大統領自らイスラエルを訪問して侵攻への「お墨付き」まで与えたのである。
ところがその後、国際社会ではむしろ戦争による「解決」を疑い、停戦を求める声が大勢となっていった。「即時停戦」決議は国連安保理では米国の拒否権行使により数度にわたって葬り去られたが、国連総会では圧倒的多数で採択され、これを受けて2024年3月には安保理でも(「ラマダーン中」という条件つきではあったが)可決(米国も「棄権」にととめざるを得なかった)に至ったのである。並行して、イスラエルのガザにおける行為を「ジェノサイド条約」違反として国際司法裁判所に提訴するという重要な動きも生じた。また、戦争ではなく交渉をめざすべきとする認識、さらに危機の背景には長年にわたるイスラエルの占領があり、解決のためにはパレスチナ人の民族自決権実現が必要だという認識が広まった結果、2024年5月にはパレスチナの国連正式加盟を支持する決議が(安保理では米の拒否権で否決されたにもかかわらず)国連総会で採択される――これに対しイスラエル代表は壇上で国連憲章をシュレッダーで裁断するという行為に出た――という展開も生じた。
現在、「即時停戦」は国際世論の大勢となった。ガザで起きていることは明らかな国際法違反、国際人道法違反であることが指摘され、さらにこれを正そうとする努力の過程で国際司法裁判所(ICJ)や国際刑事裁判所(ICC)にその機能を発揮させようとする働きかけが強まるなど、国際司法の役割への新たな期待も高まっている。そして国連も、これを無視あるいは形骸化しようとするイスラエル(およびその背後の米国)の必死の試みにもかかわらず、むしろ――国連総会が安保理を包囲し、繰り返し圧力をかけるといったダイナミズムを通じて――今回の危機の過程で新たな生命力を示し、本来果たすべき役割を追求しようとしているように見える。ガザの状況は破局的だが、これを何とか止めようとする動きの只中から、国際法や、国際法に基づく秩序を再建しようとする息吹が生まれつつあり、イスラエルや米国は追い詰められつつある――国連憲章を裁断するという光景はその象徴――と言えるのではないか。
注目に値するのは、国際社会の姿勢にこのような変化が生じるにあたり、アジア・アフリカやラテンアメリカなどの、いわゆる「グローバルサウス」の国々が重要な役割を果たしてきたことである。イスラエルによる「報復」戦争を自明視した先進国諸政府とは裏腹に、ASEAN(東南アジア諸国連合)は2023年11月に「即時停戦」を求める姿勢を示した(国防相会議議長声明)。ラテンアメリカでもイスラエルによる侵攻を厳しく批判し、断交(ボリビア、コロンビア)、あるいは大使を召還する(チリ、ブラジル等)諸国が相次いだ。とりわけ決定的役割を果たしたのは南アフリカで、イスラエルを「ジェノサイド条約」違反で国際司法裁判所(ICJ)に訴える(2023年12月)という前述の行動に踏み切ったのは同国政府だが、これはその後ICJがイスラエルに「ジェノサイド防止のためのすべての措置」をとることを求める暫定措置命令(2024年1月)を出し、これを契機に侵攻に対する国際的圧力が格段に強まることにつながった(日本の伊藤忠商事もICJのこの命令を根拠にイスラエルの軍事企業との契約終了を発表)。南アフリカはICJに対し、その後も節目節目で緊急の「暫定措置」を要請しており(現在はラファからの撤退を命じる暫定措置を要請)、これは侵攻拡大を牽制しガザの人々を守ろうとする重要な取り組みとなっている(このICJ裁判にはその後ニカラグア、コロンビア等も参加申請、アイルランドも参加の意向を表明)。