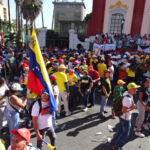南米コロンビアで、中南米最大と言われた反政府左翼ゲリラ組織「コロンビア革命軍(通称FARC)」と政府の間で和平合意が成立してから、およそ8年が経過した。
1960年代から続いた内戦では、少なくとも12万人以上が行方不明となったとされる。その中には、政府軍兵士、左翼ゲリラ、反左翼ゲリラの民兵、政府軍にゲリラ扱いされた市民など、あらゆる人間が含まれている。
現在も行方不明のままとなっている彼らの捜索のために、2016年12月に議会で承認された和平合意にもとづき設立された国家機関、「失踪者捜索ユニット(UBPD)」が奔走する。
UBPDは、全国28カ所に事務所を置き、政治社会学、犯罪学、法医人類学、地理学、ジャーナリズムなど、さまざまな知見を持つスタッフ計520名で構成される組織だ。その任務は、失踪者の捜索・発見と、失踪者と思われる遺骨の身元特定を通して、すべての失踪者を家族のもとへ送り届けること。UBPD代表のルスジャネット・フォレーロは言う。
「これまで愛する者を自力で捜索してきた家族の痛みや苦しみを、少しでも早く和らげるために、UBPDが誕生しました。内戦中の立場に関係なく、先入観や偏見抜きで、どんな失踪者も捜索するのです」
無縁墓地
2024年9月下旬、UBPDの法医人類学チームは、首都ボゴタの西に位置するトリマ県の県都、イバゲの町外れにある無縁墓地に集まっていた。そこで納骨室2カ所を5日間かけて調査し、政府軍に殺害されたFARC戦闘員3名の遺骨を見つけるためだ。幅4メートルほどの塀のような構造物の両側に並ぶ納骨室の扉の大半には、遺体が運ばれてきた年月日と順番を示す数字しか書かれていない。誰がそこに眠っているかは、納骨時期から予測し、遺骨を鑑定して確認するしかない。
朝8時。調査責任者の法医人類学者フアンカルロス・ベナビデスとチームメンバー3名が、今回開ける2つの納骨室の裏手にテントを設置し、簡易テーブルを何台か並べていく。鑑定作業場の設営だ。その間にも、捜索対象となっている失踪者の遺族やその友人、和平合意の遂行状況を確認する国連関係者らが集まってくる。
それからまもなく、UBPDの地域コーディネーターの呼びかけにより、居合わせた全員が、納骨室の脇の広場で手を取り合って輪になった。
「作業を始める前に、みなさんの間に調和の空気を生み出したいと思います」
香が焚かれるなか、全員で「歓喜の歌」をうたい、最後に近くの者同士、抱擁を交わす。
実は、この調査に立ち会う失踪者の遺族2組は、立場がまったく異なる。1組は、22歳でFARCに入隊を強要されて戦死した男性の妻と娘で、もう1組は、FARC戦闘員で政府軍の捕虜になった末に殺害された兄を探す、自身も元FARC戦闘員である弟と元FARCの仲間だ。
法医人類学者のフアンカルロスが、遺族にこう語りかける。
「私たちは今日、みなさんのためにここにいます。遺骨を見つけ出し、(失踪後の)長い間、みなさんが抱いてきた心の痛みを、少しでも癒すことができればと思います」
法医人類学チームは、まず1つ目の納骨室の扉を、データ記録用の写真に収めたうえで鑿とハンマーでこじ開け、納められているビニールの遺骨袋14個を、1つずつ運び出した。袋は作業テーブルに並べられ、番号札が付けられたうえで順に開封され、取り出された骨が別のテーブルに置かれる。チームは、その骨や歯などを鑑定し、性別や年齢、身長、死亡理由などを調べていく。それらのデータと、検察での検死の記録や歯科の記録、遺族からの聞き取りなどからわかった特徴と照らし合わせて、身元の特定を目指す。ほぼ特定された場合は、首都にある法医学研究所へ持ち帰り、さらにDNA鑑定などを行ない、身元を確定する。
1日目の作業は成果が上がらないまま終了し、迎えた2日目。ボゴタから派遣された検察官が率いる検察法医人類学チームが合流し、UBPDと協同で鑑定作業にあたる。2つ目の納骨室が開けられ、そこから出された遺骨袋も前日の分と合わせて調査される。
法医人類学チームの作業場は、立ち入り禁止のテープで囲まれているため、遺族やその付き添いの人々は、少し離れたところから鑑定の様子を見つめている。運び出された袋は計29あり、すべて鑑定し終えるまでには数日かかる。探している遺骨は今日見つかるかもしれないし、明日、明後日かもしれない。見つからない可能性もある。
真実を知る
「それは私が16歳、娘はまだ1歳だったクリスマスシーズンのある夜のことでした。熱を出した娘の看病をしている私を残し、(夫の)オルランドは村のパーティに出かけたんです。翌朝、私が会場へ探しに行った時には、もう姿がありませんでした」
14歳で結婚した相手がそのわずか2年後に失踪したビルへリーナ(39歳)は、失踪時の様子を、そう語る。FARCの支配地域だったトリマ県南部の農村地帯のパーティ会場からは、オルランドを含む5人の若い農民がゲリラに連れ去られた。妻は、検察に捜索願を出して夫を探しつづけたが、行方が掴めないまま月日は流れ、死亡の知らせもなく、最後は「どこかで生きているものだと思っていました」と言う。ところが、今回の調査の数カ月前、検察から「遺骨確認の際にDNAを照合するために、血液サンプルを採取したい」との連絡があり、その死を知ることになる。
「この時、父はもうこの世にいないと確定したんです」と、娘のマリアイサベル(24歳)。母娘は、検察に「失踪から半年後、政府軍との戦闘で死亡した際の検死の記録が見つかったが、埋葬場所は不明」と知らされ、再び遺体を探すことになった。
「それから1カ月も経たないうちにUBPDからの連絡で、この墓地に埋葬されている可能性を知りました。おかげで予想よりも早く見つかりそうです」
ビルへリーナはUBPDに感謝を示しながら、遺骨の発見を待つ。
調査を担当したUBPDトリマ県の調査スタッフ、クラウディア・ベルトラン(40歳)は、この地域で活動していたFARCの元戦闘員からの情報と検察からの情報を突き合わせた結果、オルランドが参加した戦闘での死者がこの墓地に埋葬されている可能性を突き止めたと説明する。
「この墓地に関する全資料を調べてそれを確認し、今回の調査にこぎつけたのです」
クラウディアの話の間に、検察の法医人類学者は、タブレットに保存された検死の記録と照合しながら、オルランドと見られる遺骨の鑑定を進めていた。遺体の入った袋に付いていたタグの情報との比較や、年齢、体格、歯の状況などから、ほぼ特定できると言う。
検察の資料の中には、検死時に撮影されたオルランドの写真も含まれていた。スマートフォンの薄暗い画面に浮かぶ、ややぼやけたモノクロ写真は、静かに目を閉じた若い男性の顔。23年ぶりに目にする夫の姿に、それまで気丈にしていたビルへリーナが泣き崩れ、娘に抱きついた。娘はほとんど記憶のない父の顔を食い入るように見つめた後、母をぐっと抱き寄せる。
それから少しして、2人は検察の法医人類学者に案内され、オルランドの遺骨と対面した。「どんな人でしたか?」と尋ねられ、一瞬戸惑うビルへリーナに、法医人類学者が「娘さんに似ている?」。「そう、こういう目をしていました」と、ビルへリーナは娘のほうを見て微笑む。
どこかで生きている。そう信じたままでいたほうが幸せだったのでは――。心境を尋ねると、母娘からはこんな答えが返ってきた。
「泣けたことで、少し気が楽になりました。悲しいけれど、真実を知ることは、とても大きな安らぎを与えてくれます」

本文中の写真はすべて撮影:篠田有史
この後、遺骨は法医学研究所でDNA照合などの正式な鑑定作業を経て、2人のもとへ帰ることになる。過去を問い直す安堵する母娘から数メートル離れたところには、数人の男たちと女性に付き添われ、兄の遺骨の発見を待つ元FARC戦闘員、ビクトル・オソリオ(35歳)の姿があった。付き添っているのは元FARCの仲間と、彼らの社会復帰を支える政府機関の女性職員だ。
ビクトルと5つ歳上の兄アレクサンデルは、FARCの拠点となっていた貧しい農村に生まれた。貧困問題の解決に動かない政府に抗議する農民たちの中から生まれたFARCは、その村では貧困家庭の子どもや若者の支援者でもあった。
「私が中途入学できるように学校と掛け合ったり、文具を提供してくれたりしたのは、FARCの人でした。だから、私も兄も迷うことなくゲリラに参加したのです」
10歳の時から20年近くをゲリラ仲間と過ごしたビクトルにとって、仲間こそが「家族」だった。
「15歳になった時、もう家に帰ったほうがいい、と言われました。でも、私は仲間と離れたくなかったため、残りました」
兄が政府軍の捕虜になり殺害されたことは、ニュースで知った。しかし、当時は内戦の真っ只中で、遺体の捜索や返還を求める術はなかった。
「UBPDが、私たちの証言やニュース記事、墓地や遺体安置所などから、あらゆる情報を集めて調べてくれました。その結果、兄の遺体は何カ所かを転々とした後に、ここにたどり着いた可能性が高いとわかったんです」
そう語るビクトルは、兄の捜索と同時に、UBPDの失踪者捜索活動全般にも協力している。元ゲリラが、戦闘のあった地域や敵の遺体の埋葬場所など、失踪者の捜索に役立つ情報をUBPDに提供したり、その捜索活動に同行したりする場合は、法の裁きの対象にならないことが、和平合意で定められた。それを受けて、ビクトルを含む元FARC戦闘員たちは、ボランティアのグループ「レエンクウェントロ」を結成し、捜索活動に協力。グループ名は「再会」を意味する。今回、彼に付き添っているのも、その仲間だ。レエンクウェントロは、内戦中の立場に関係なく、あらゆる失踪者を見つけようとしていると、ビクトルは言う。
「私たちを決して許さない人は大勢います。あまりにも長い年月続いた暴力を、一度の抱擁や謝罪の言葉で消し去ることは難しい。それでも被害者の多くは、憎しみより真実を知ることを優先しています。それこそが、社会を再構築するために必要なことだと感じているからです。そのために、自分たちができることをしたいと思います」

すべての失踪者の捜索に協力したいと話す。
貧困に苦しむ人のいない社会を築こうと戦っていたつもりだったが、和平合意を経た今、武力行使は間違いだったと考えている。
「当時の状況や理想を言いわけに行使した暴力が、社会に多くの犠牲を強いたことは否定できません。だからこそ、失踪者の捜索に貢献することで、社会への責務を少しでも果たしたいのです」
ビクトルは、現在、元FARCの仲間の多くが所属する「国立警備ユニット」(ボディガード組織)で働き、その労働組合の代表を務めながら、大学で心理学を学んでいる。心理学は、内戦中にゲリラが行なった、通常なら考えられない残虐行為がなぜ可能になってしまったのか、理解するのに役立つと思うからだ。
「兄も、生きていれば和平合意に賛成し、対立は対話によって解決すべきだ、と言ったでしょう。この社会の問題は、暴力や撃ち合いで解決できるものではない。今はそう感じています」
彼らFARCのせいで夫を失ったビルへリーナと娘のマリアイサベルにも、和平合意について尋ねてみると、こう答えてくれた。
「FARCは憎いです。でも、和平合意は実現して良かったと思います。それがなかったら、どうなっていたことか」
内戦では、大勢が失踪したり殺害されたりしただけでなく、彼女たちを含む多くの人が、戦闘を逃れて故郷を離れざるを得なかった。そんな現実を変えるには、和平が不可欠だったのだ。
事前調査と協同が鍵
立場も法の枠も超えた、人道目的の協同作業によって進められている失踪者の捜索。イバゲの無縁墓地での調査では、最終的に、発見を目指していた3名全員の遺骨を特定することができた。また、今回の捜索対象にはなっていなかったが、内戦中の犠牲者と思われる遺骨も、何体か見つかった。それらは今後、「逆追跡」、つまり遺骨の発見経緯や特徴から推測して調査を進め、遺族を探し出すことになる。
調査を指揮した法医人類学者のフアンカルロスは、法医人類学チームの作業が成果を上げるには、クラウディアらが行なう細かい事前調査が、もっとも重要だと指摘する。
「コロンビアは、法医学が進んでいる国の1つです。しかし、しっかりとした事前調査と記録がなければ、失踪者を探し当てることはできません。捜索対象者の特徴を示すしっかりとした記録と居場所についての事前調査が、私たちを失踪者発見へと導くのです」
実際、トリマ県での調査を担当するクラウディアは、事前調査として、およそ3年前から、この地域全体の状況を視野に入れた形でイバゲの無縁墓地の記録を調べている。
「私たちは、ある特定の失踪者が見つかる可能性のみを調べているのではなく、その人物と同じ場所、同じ事件で失踪した人がいないか、捜索願の出ている別の失踪者とつながる記録はないか、捜索願は出ていないが内戦中の失踪者である可能性が高い人はいないかなど、あらゆる角度から失踪者にたどり着く可能性を探っています」
その際、失踪者をただ発見するだけではなく、どういう経緯でそこへたどり着いたのかなども、詳しく調査することにこだわる。
「私たちの仕事は、できるだけ多くの失踪者をできる限り早く発見することであるのは、間違いありません。でも、それだけではない。愛する人を探す人の『知る権利』を保障することでもあるのです。それがすべての人の癒やしにつながります」
クラウディアは、そう確信している。
UBPDは、その設立以前から行方不明の家族を捜している市民グループなど、500近い個人・団体と連携し、先に触れたレエンクウェントロや検察とともに、調査・捜索活動を展開する。それと同時に、UBPDの活動がまだあまり知られていない地域での広報活動を強化し、まだ出会っていない失踪者家族とのつながりを築こうとしている。それが、失踪者の発見をスピードアップし、真実を明らかにすることに役立つと考えるからだ。
あらゆる失踪者の帰還を
UBPDには、これまでに3万人近い失踪者の捜索依頼が寄せられている。そのうち、約2000人がすでに発見された。その大半は遺骨として家族のもとへ帰ることになったが、生きて家族との再会を果たせた者も、40人近くいる。
家族の再会を可能にするために、UBPDは、身元特定に使われるDNA鑑定に必要なデータがまだない失踪者家族からは、検察に代わって血液サンプルの採取も行なう。居住地が遠いなどの理由で、UBPD事務所まで来ることができない場合は、スタッフが自宅へ赴き、指から6〜8滴の血液を採取して、得たサンプルを国立法医学研究所へ送り、データ化する。
捜索願が出ていない失踪者の存在や遺骨の身元を探るべく、過去60年余りの新聞・雑誌記事から手掛かりとなる情報を見つけ出すスタッフもいる。ボゴタにある中央事務所では、国立図書館へスタッフを派遣し、そこに所蔵されている新聞や雑誌を年代別に調べている。担当スタッフのフアンルイス・マルティネス(57歳)は、その意義をこう述べる。
「たとえば、タブロイド紙には、当時は誰も気に止めなかったけれど、本当は重要な手掛かりとなる新事実が掲載されていたりします。そうした情報をていねいに集めることで、より多くの失踪者にたどり着けます」
加えて、外国人の失踪者の捜索にも携わる。
「先日は、国境地帯で失踪していたエクアドル人の遺骨を発見し、エクアドル政府との連携によって、国境の橋で遺族に引き渡すことができました」
引渡しを担当したスタッフが、そう教えてくれる。5カ国と国境を接するコロンビアでは、内戦に巻き込まれて失踪した外国人、特に隣国の住民が相当数いると推測されている。彼らを発見し、母国の家族のもとへ帰すために、東隣のベネズエラ政府とはすでに緊密な連携をとっており、エクアドル政府とも共同捜索の合意書を作成しているところだ。

UBPDの捜索活動の意義と同時に、国内数カ所で依然として戦闘が続く状況下での捜索の困難を、語った。

この仕事は、心身への負担が大きいが、重要で、天職だと思っている。



政府軍の捕虜になったFARCメンバーの顔がはっきりとわかる写真が掲載されていた。
その中には少年の姿も。
真の平和を築くために
今なお存在する、12万人を超える失踪者。
「それはあくまでも検察や法医学研究所、70〜80年代から失踪者情報を収集している市民グループなどの協力のおかげで登録できた人の数です」
そう話すUBPD代表、ルスジャネットは、実際にはその倍の人数の失踪者がいる可能性があると見ている。UBPDの誕生以降、それまで知られていなかった失踪者の存在が、8000件以上も明るみに出たからだ。
現状から、「1日に1人発見できたとしても、(全員発見するには)300年はかかります」と認めつつも、「毎日1人は見つけ出して家族のもとへ帰すことが叶い、愛する人を何年も探しつづけていた家族の痛みや苦しみを癒やすことができたなら、私たちのもっとも大切な使命は果たせていると言えるでしょう」と、UBPDの活動の中に光を見出す。
コロンビアでは、いまだに複数の地域で、主にコカインの生産・密輸の支配などをめぐり、反政府左翼ゲリラ組織「民族解放軍(ELN)」やFARCの残党などの異なる武装組織同士、あるいは彼らと政府軍との間で、戦闘が続いている。その一因は、内戦による社会の分断が解消されておらず、武装組織を離れて生きることをためらう者がまだ大勢いることだろう。そんな状況下でも、なおUBPDが立場を超えた人々の協働によって失踪者を発見してきたことは、大きな希望だ。数字で示せる成果は小さいかもしれないが、その活動精神は、世界の紛争地において真の平和を実現するために、もっとも重要なことを伝えている。
ルスジャネットは、強調する。
「平和とは、和平合意に署名することではありません。署名後に起こす、新しい制度や社会の構築、価値観の変革、非妥協から妥協への移行、叶わなかったことを叶える努力のことです。長い対立の終結には、すべての関係者がひとつの場に集い、『これまでとは異なる現実』を創るプロセスに立ち会うことが欠かせません。UBPDの活動は、それを少なからず実現してきたと思います」