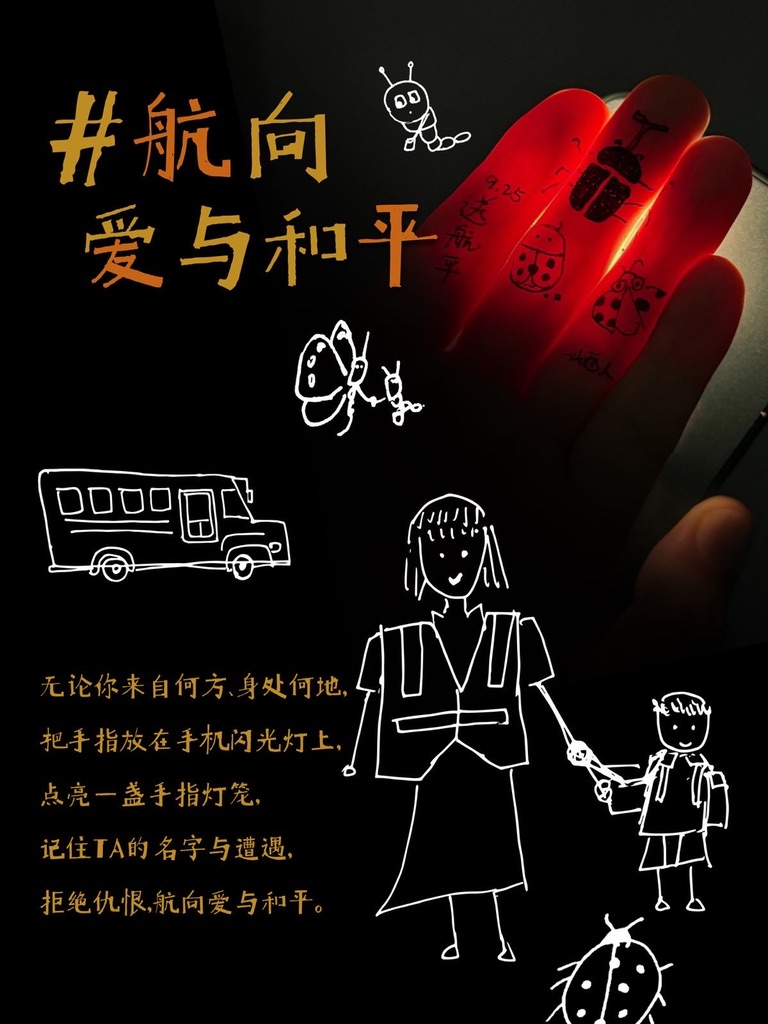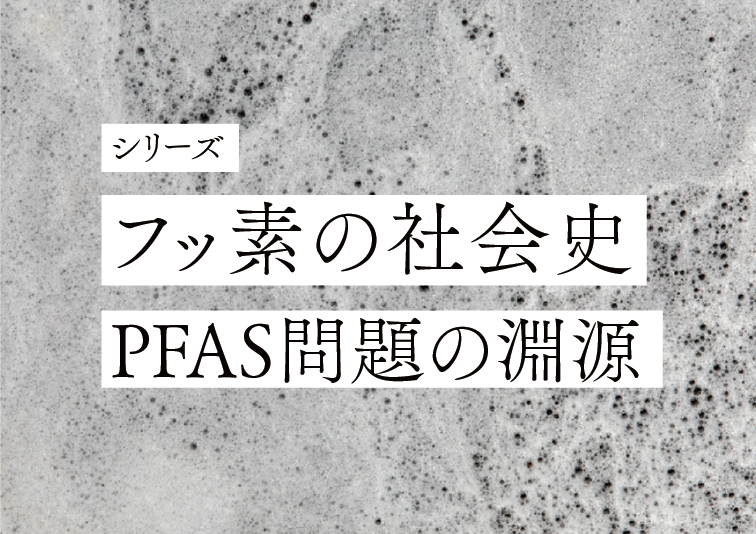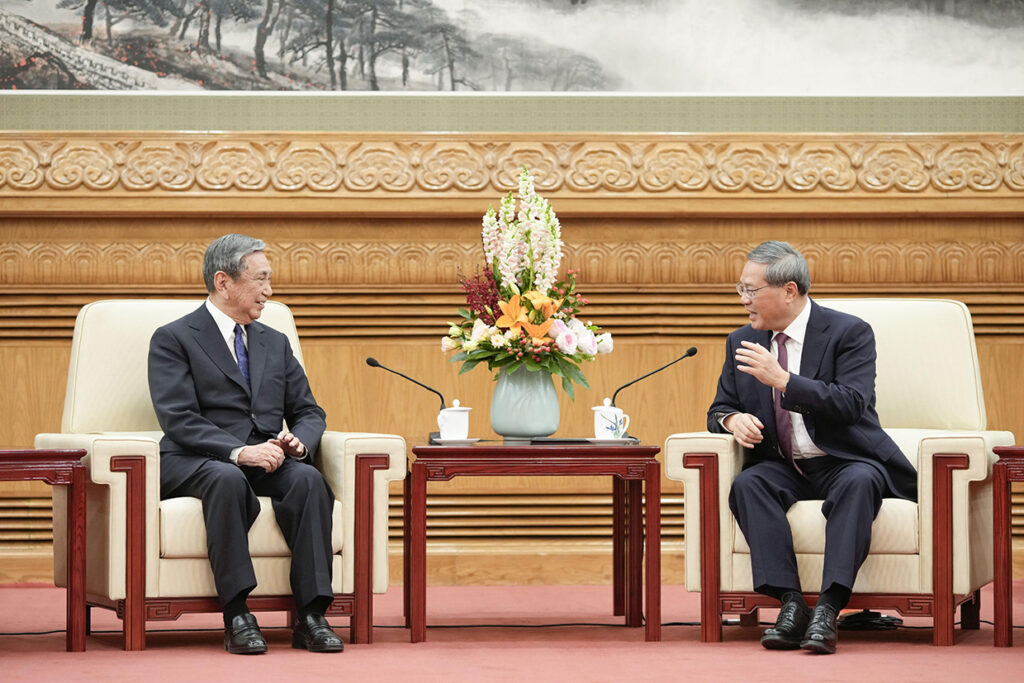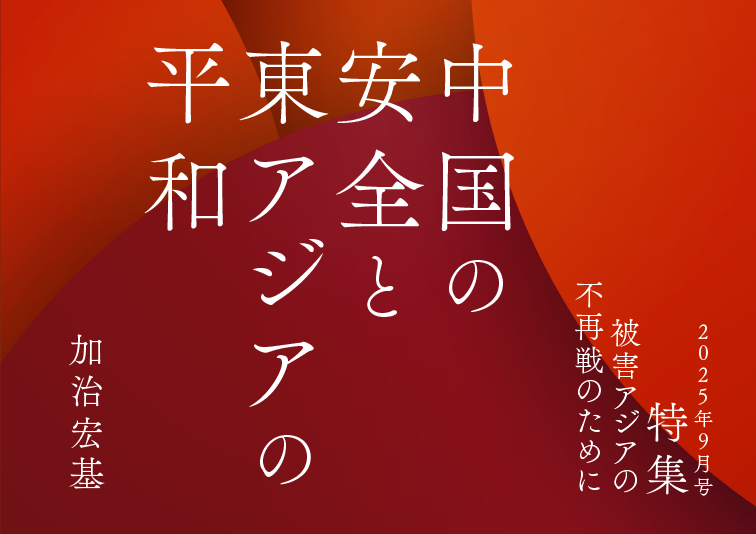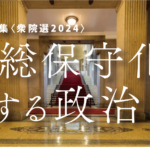社会不安の増大
この原稿について考えながら、携帯電話でXを眺めていた時、日本で暮らしているとみられる中国人女性の投稿が目に入った。「上海の経済がこれほど悪くなっているとは思ってもみなかった。6人の同級生のうち4人が失業中だって」。その下には、ずらりと多くのコメントがついている。
「本地人(上海の戸籍を持つ地元の人)は焦る必要ないさ。外地人(上海の戸籍を持たず上海で暮らす人)は失業したら起業もできない」「勤続年数によるみたいだけど、上海人は、毎月2000元の失業救済金が2年間はもらえるみたい」「同済大学(上海の一流大学)を卒業した私の親戚の子も仕事がなくて、家で寝そべり族よ。でも、上海人の一般家庭は恵まれているから、車も家もあって、子どもを養うのは問題ないわ」「そんなの当然よ。去年から上海でリストラしてない外資企業なんてある? でも、一部の人は家ですねかじりしていればいいんだから。蓄えもあるでしょう。今後十数年、住宅ローンを抱える子育て世帯は悲惨なことになる。上海の本当の危機はまだ始まっていない」――。
中国の景気回復は思うように進んでおらず、特に若年層の失業率は高止まりしている。「卒業即失業」という言葉が流行語にまでなっているように、中国の国家統計局が発表した2024年8月時点の16歳~24歳の失業率は18.8%と、およそ5人に一人の大学生は卒業しても仕事がない状態だ。
さらに、とりわけ、経済不況の影響を受けているのが、冒頭で紹介したように「外地人」だと言える。中国には毛沢東時代から続く戸籍制度があり、社会保障の条件が良い上海や北京など大都市の戸籍を得ることは難しく、大都市で働いていてもその地の戸籍を持たない「外地人」の多くは所得が低く、不動産など財産もほとんどなく、リストラの対象とされやすい状況だ。
社会不安も増しており、私が定期的に目を通しているソーシャルメディア(SNS)では、具体的な動画や写真の説明がつけられた中国各地での殺傷事件のニュースを目にすることが多くなった。そして、いわゆる「反日」的な動きも活発になっている。
起こるべくして起こったのか
そんななか、蘇州で6月に日本人学校スクールバスへの襲撃事件が起こり、9月には深圳の日本人学校に通う10歳の男児が男に襲われて亡くなった。9月18日は1931年の満州事変の発端となった柳条湖事件が起きた日で、中国では「国辱の日」とされている。
事件はなぜ起こったのか。犯人の男の動機は何だったのか。中国政府からは依然として説明がほとんどないが、10月18日付の読売新聞は、事情を知る中国当局者に近い関係者の話として、職探しがうまくいかず不満をもっていた男が、「『何か大きなことをすれば自分が注目され、日本人を刺せば反響が大きく、自分を支持してくれる人もいるだろうと思った。日本人学校の場所はネットで探した』との趣旨の供述をしている」と報じた。私の旧知の中国人の識者は、深圳と蘇州の事件の犯人はともに、「外地人」による犯行の可能性が高いと述べた。
いずれにせよ、こうした情報だけで「日本人を狙った」という推測を安易にすべきではないが、短い期間に連続して日本人学校が狙われた事実について考えることは重要であろう。