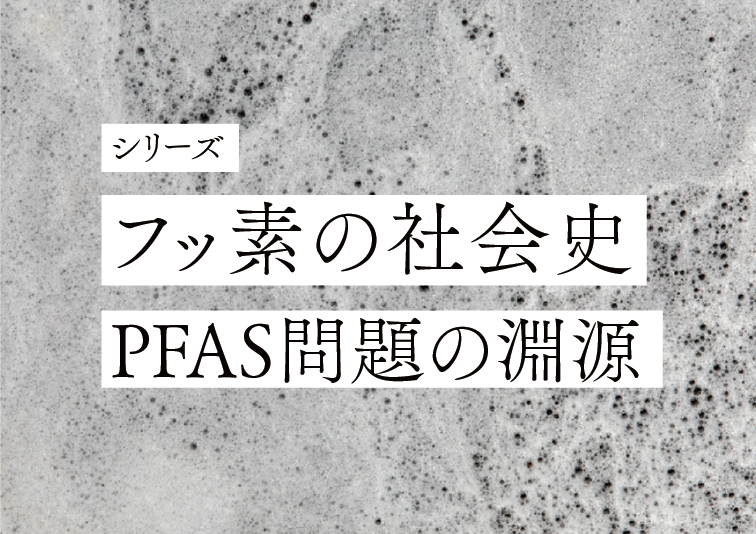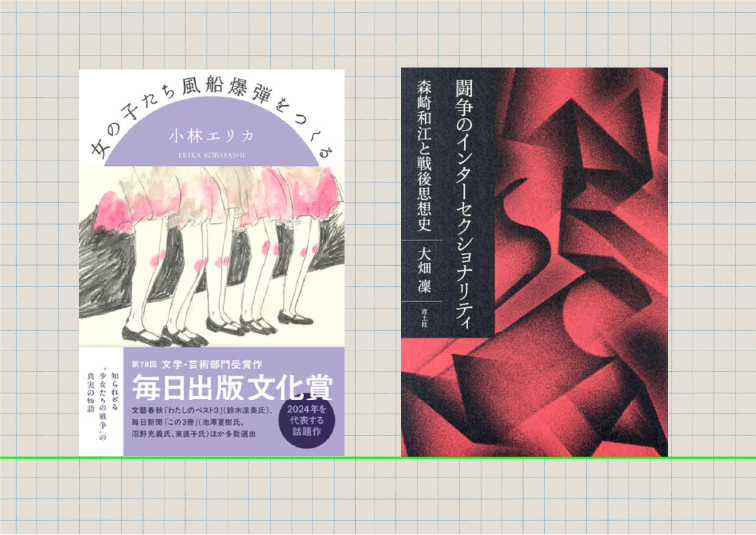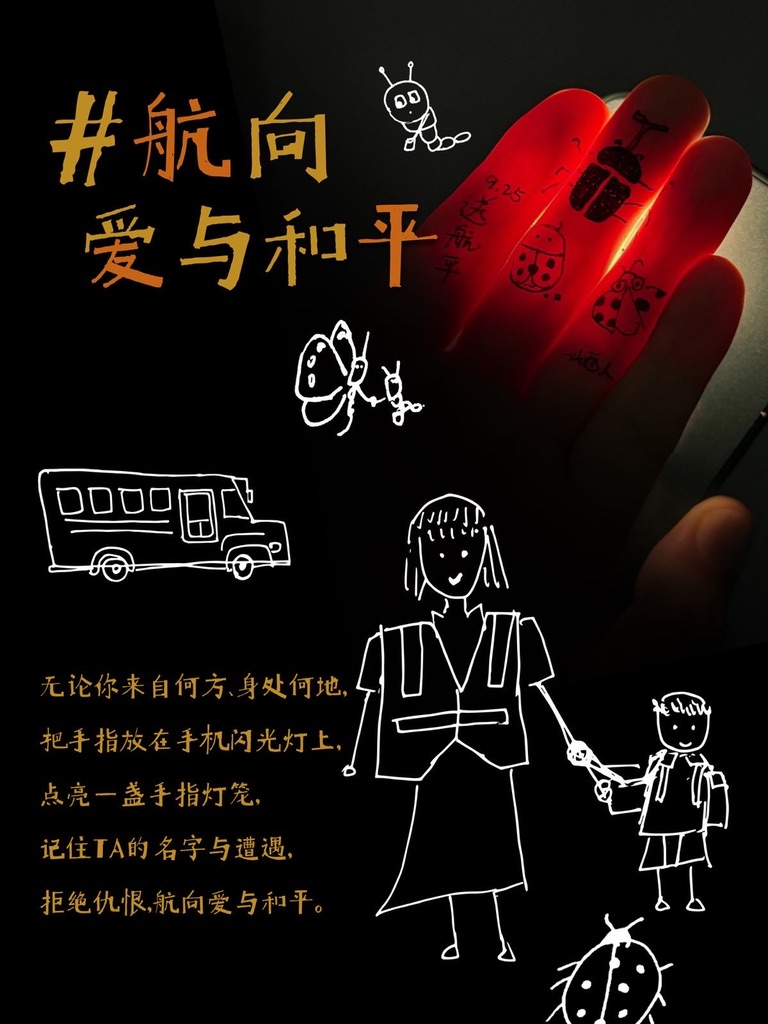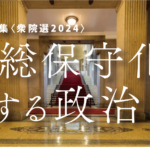フッ素が含まれるくすり
フッ素を用いたくすりが、増えつづけている。データによると、1991年から2011年の間で発売されたくすりの中でフッ素が含まれているものは、645のうち92(14.3%)で、ずいぶん増えてきたと思っていたところ、2012年から2019年の間では、427のうち99(23.2%)と、さらにその割合が増加していた。
なぜ、増えたのか。そこにはフッ素の持つ独特の性質がある。その性質で最大の特徴がミミック効果と呼ばれるもので、フッ素と水素の大きさがほとんど変わらないことから、置き換えても構造に変化を与えず、体が認識しにくいという点である。しかし、水素をフッ素に置き換えたことで、その性質は変わり、その違いを利用して医薬品が開発されてきた。もう一つの大きな特徴が、結合力が強く、効果が長く持続する点である。これは農薬の効果でも述べたが、またPFASが「永遠の化学物質」といわれる所以でもあるわけだが、くすりでは極めて有効に働く。その結果、フッ素を含んだくすりが増えつづけているのである。
そのミミック効果を利用したくすりの代表に、抗がん剤の5‐フルオロウラシル(5FU)がある。1950年代に登場して、今日まで利用され続けている抗がん剤の代表である。その5FUを見ていく前に、抗がん剤の歴史を見てみよう。
抗がん剤の出発点は毒ガス兵器
戦争は、新たな科学技術を生み出す宝庫である。その最大の理由は、人体実験などに倫理的規制が働かなくなるからである。政府や企業にとって、あるいは研究者なども含めてあらゆることが、戦争に勝つことが目的とされ、平時には重要とされる安全性や倫理性が二の次にされ、人体実験も行ない放題になってきた。そのことがくすりの開発でも行なわれた。臨床試験が必要なくすりにこそ、戦争は“絶好のチャンス”をもたらしてきたといえる。
抗がん剤の歴史は、農薬と同様、毒ガス兵器が起源となって始まる。第一次世界大戦の際、さまざまな毒ガス兵器が開発され、使用された。塩素ガス、ホスゲン、青酸ガスなどの血液ガス、イペリット、ルイサイトといったびらん性ガスである。びらん性ガスとは、皮膚や気道などをただれさせる効果があることから、この名がつけられた。
毒ガス兵器の開発は、それがどのように健康を害するのかという生体への影響の解明とともに、それに対する防御策の開発もともなっている。その過程で、イペリットが抗がん剤になり得るとする研究成果が登場するのである。
核・生物・化学兵器=ABC兵器は、その防御策を含めて開発されてきた。例えば生物兵器では、病原性ウイルスや細菌を用いて兵器を開発する際にはワクチン開発が必須である。兵器を使用した地域に味方の兵士も入っていかなければならないからである。そのためワクチン開発を見ることで、生物兵器開発の状況が分かる。毒ガス兵器もまた、同様の理由で防護方法と同時に開発されてきた。
イペリットはからしに似た臭いから「マスタードガス」と呼ばれていた。このマスタードガスが、実はがんに対する効果もあるのではないか、という見解が示された。それは毒性を強めたり、防御方法を開発したりする中から示されたのである。強い臭いは兵器としてはマイナスになることから、臭いを消すために構造の中の硫黄をチッソに置き換えたものが開発された。それがナイトロジェン(窒素)・マスタードといい、1935年にチェコスロバキア(当時)の科学者によって合成された。この毒ガス兵器を用いて160人に及ぶ人体実験が行なわれ、ある種のがんに対する効果が確認されたとして、戦後、史上初の抗がん剤ナイトロジェン・マスタードが誕生するのである。
5‐フルオロウラシルの誕生
ナイトロジェン・マスタードは、アルキル化反応によって効果をもたらす。アルキル化反応とは、DNAやRNAといった核酸にメチルやエチルといったアルキル基をくっつけることで起きる反応で、この反応ががん細胞にダメージを与える。このようなくすりをアルキル化剤という。しかし、この反応はがん細胞だけでなく正常な細胞でも起きるため、強い副作用が問題となった。毒を以て毒を制するという考え方は、全身に影響するのである。
次に登場したのが、代謝拮抗剤と呼ばれる抗がん剤である。生命の基本的な活動である代謝にとって必要な物質にそっくりな物質を作り、活動の歯車に変調を与えるというものである。最初に登場したのは葉酸に類似した物質である。葉酸は、造血性を持つビタミンである。葉酸の働きの歯車を狂わせることで、がん細胞にダメージを与えようとするもので、1947年に米国アメリカン・サイアナミッド社(現ファイザー社)レダリー研究所によって開発された。それがアミノプテリンというもので、次いで構造を少し変えたアメトプテリンが抗がん剤として登場した。