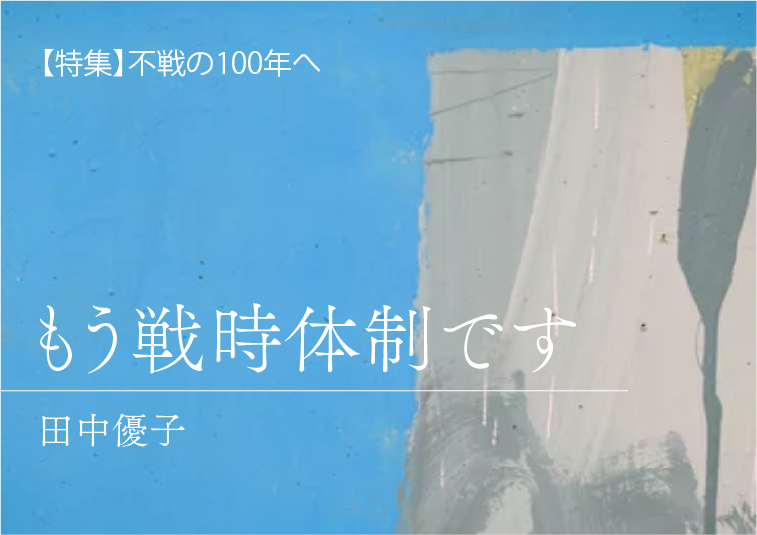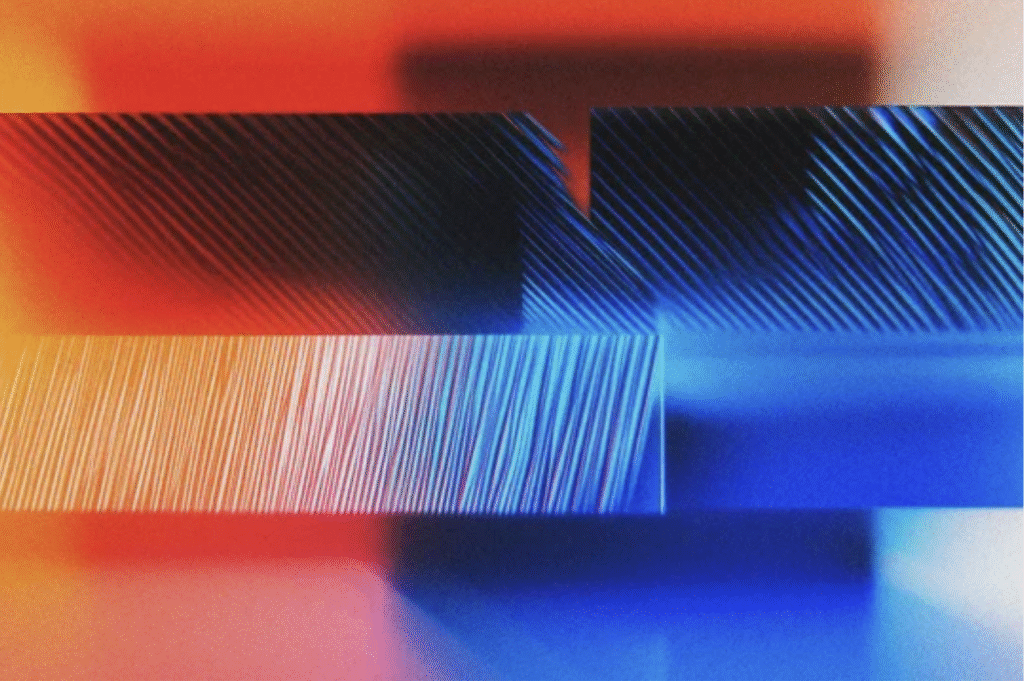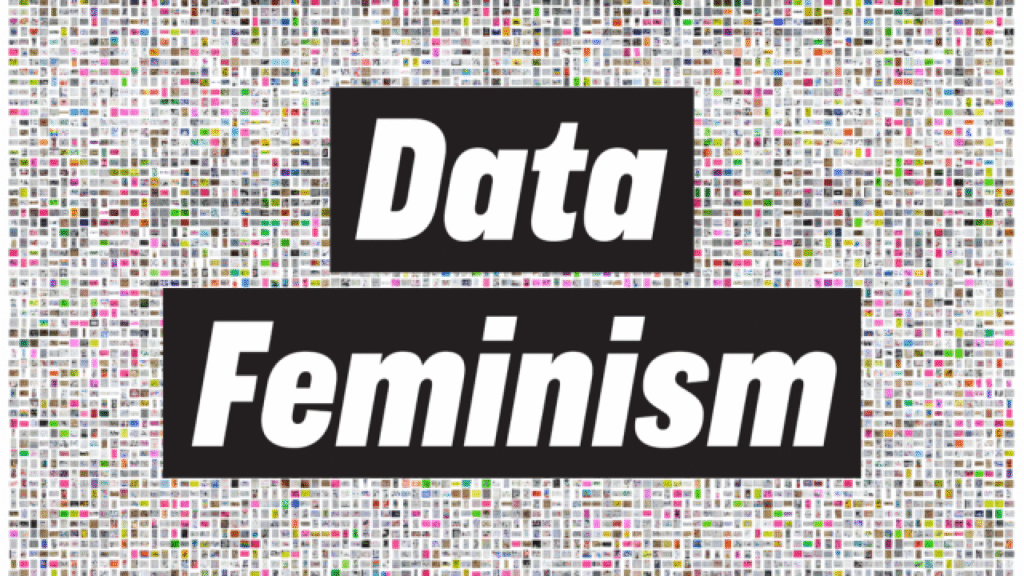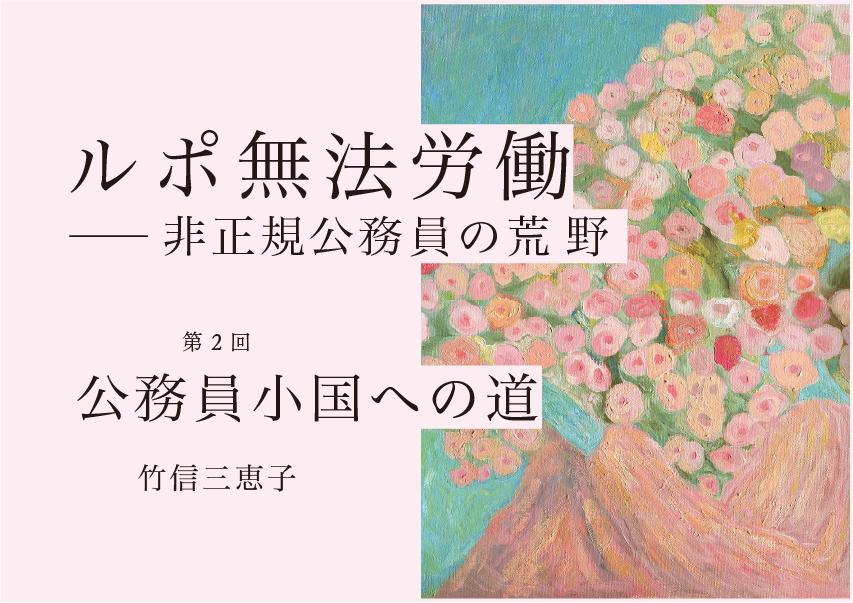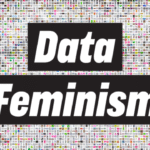多くの犠牲者を出したコロナ禍を経てもなお、医療費抑制政策の転換は行なわれず、それどころか、医療費抑制政策が加速している。
コロナ禍の医療崩壊と「いのちの選別」
2020年2月以降の日本での新型コロナウイルス感染症(COVID‐19)のパンデミック(爆発的感染拡大)は、医療をはじめとする日本の社会保障の制度的脆弱さを浮き彫りにした。
感染拡大の波は3年以上にわたり繰り返され、感染拡大地域では、入院できる病床や医療従事者の不足で、多くの感染者が入院できず、高齢者施設の高齢者や精神科病院の精神障害者は施設等に留め置かれ、国民皆保険制度が確立しているはずの日本で、必要な医療を受けることができないまま亡くなる人が続出したのである(自宅放置死や施設留め置き死といわれる)。本来であれば救える命が救えない「医療崩壊」が生じ、医療現場では「トリアージ」を名目に、高齢を理由に人工呼吸器の利用を拒否される、認知症や精神疾患のある患者の入院が対応困難との理由で忌避されるなど、とくに高齢者や障害者について入院治療の優先順位が低位に置かれる医療差別がさまざまな場面でみられた。
しかし、自民党・公明党連立政権(以下「自公政権」という)は、ワクチン接種以外は、十分な対策をとらず、こうした医療崩壊の状況を放置した。そもそも、医療崩壊が現実化した背景には、病床の削減や医師数削減を続けてきた自公政権の医療費抑制政策がある。しかし、そうした医療費抑制政策は転換されることなく、自公政権は、コロナ禍でも病床を削減しつづけ、医療提供体制や検査体制の整備をしないまま、新型コロナの感染症法上の位置づけを、季節性インフルエンザと同等の5類感染症に引き下げた(2023年5月8日)。
そして、5類移行後は、マスコミでも、コロナ関連の報道は激減し、感染者数も死者数も、数カ月遅れての推計からの発表となり(厚生労働省の発表では、5類移行後1年間で、コロナ感染による死者数は3万2000人にのぼるとされており、2024年5月時点で、死者数は累計で13万人を突破している)、正確な数は闇の中だ。ドイツなどヨーロッパ諸国では、コロナ政策の検証をきちんと行ない、新型コロナの特性変化など科学的根拠に基づいて柔軟に政策を転換し対応してきたが、日本政府は、医療崩壊を引き起こした医療提供体制の不備、公衆衛生の脆弱さについて十分な検証も行なわず、コロナ禍の自宅放置死や留め置き死も「しかたがなかった」出来事として忘却のかなたに葬り去ろうとしている。
しかし、医療にかかれず死亡された人がこれだけ存在した事態を「しかたがなかった」と、すませることはできないのではないか。このままでは、次に新興感染症のパンデミックが到来した場合(多くの専門家が確実に到来すると予想している)、再び病床のひっ迫による医療崩壊と「いのちの選別」が繰り返されることは目に見えている。何よりも、虚弱な高齢者や障害者がコロナで亡くなっても仕方がない、何人死のうが無関心という戦慄すべき雰囲気が日本社会に醸成されつつある。
そして、多くの犠牲者を出したコロナ禍を経てもなお、医療費抑制政策の転換は行なわれず、それどころか、75歳以上の高齢者の2割負担導入といった窓口負担の引き上げや保険給付の範囲の縮小、病床のさらなる削減など、医療費抑制政策が加速している。
本稿では、医療費抑制政策の動向を、すでに実施されている長期収載医薬品の選定療養化に加え、OTC(市販薬)類似薬の保険給付の見直し、そして高額療養費の見直しを中心に考察し、医療費抑制政策の転換に向けた課題を展望する。