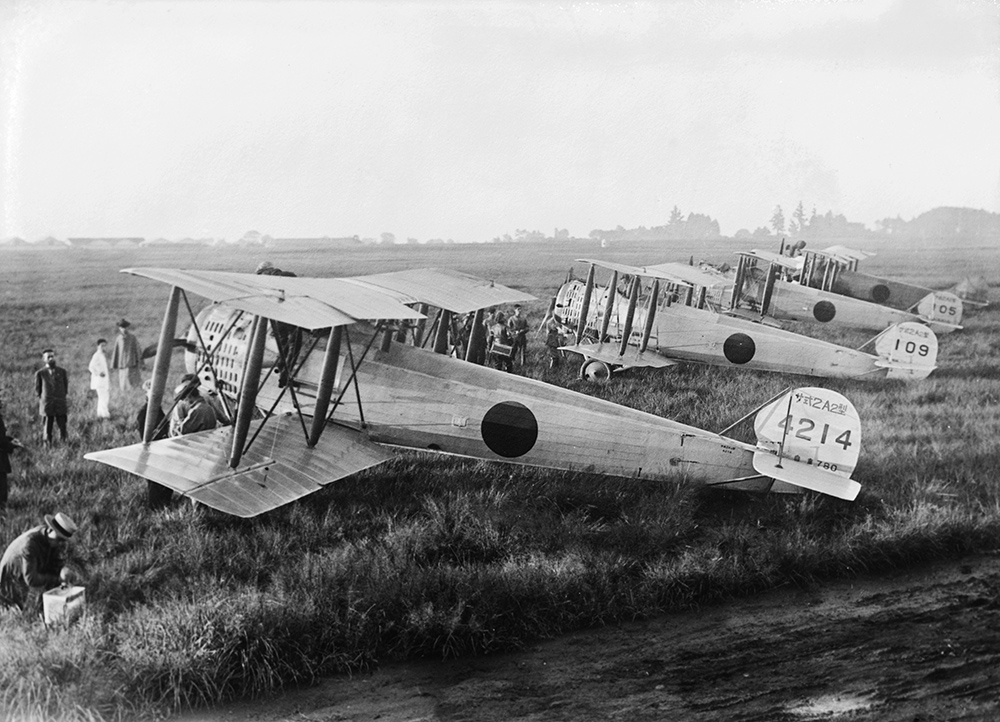はじめに
2022年12月に閣議決定された「防衛力整備計画」によれば、2023~27年度の5年間で防衛費累計額は43兆円(人件費・糧食費11兆円、兵器・弾薬等の物件費等32兆円)が予定されている。その前の「中期防衛力整備計画」(2019~23年度)では5年間の所要経費27.5兆円(人件費・糧食費11兆円、兵器・弾薬等の物件費等16.5兆円)であったことと比べても大幅な拡充である。
各年度の防衛費予算額でみても、2019~22年度には5.2~5.4兆円であったが、2023年度6.8兆円、24年度7.9兆円を経て、27年度には8.9兆円に増額される。
2027年度に向けての増額を賄う財源として、政府は次の二つをあげている。①国民負担を抑えるための工夫で必要財源の4分の3を確保する。つまり、決算剰余金の活用、防衛力強化資金(税外収入)、歳出改革によって毎年度3兆円を確保する。②それでも不足する毎年度約1兆円の財源については、2023年度税制改正大綱では法人税、所得税、たばこ税を段階的に増税し、2027年度には1兆円を確保するとしているが、具体的増税計画はいまだ不明である。
さて、第二次世界大戦後の日本の国家財政において、これまで防衛費増額を理由にした増税は実施されたことはない(ただし、1990年度補正予算での湾岸戦争支援財源のための法人税、石油税の臨時特別税はある)。そうした中で今回、防衛費増額を実現する財源の一部として増税の可能性が提起されているわけである。しかし他方で、戦前に目を転じれば、日本の国家財政では明治期以降から第二次大戦にいたるまで、度重なる戦争と軍備拡張のために大規模な増税を繰り返してきたことも事実である。そこで本稿では戦前期における日本の軍事費と増税の関係を簡単に振り返り、今日の防衛費増額と増税を考える際の参考材料を提供することにしたい。