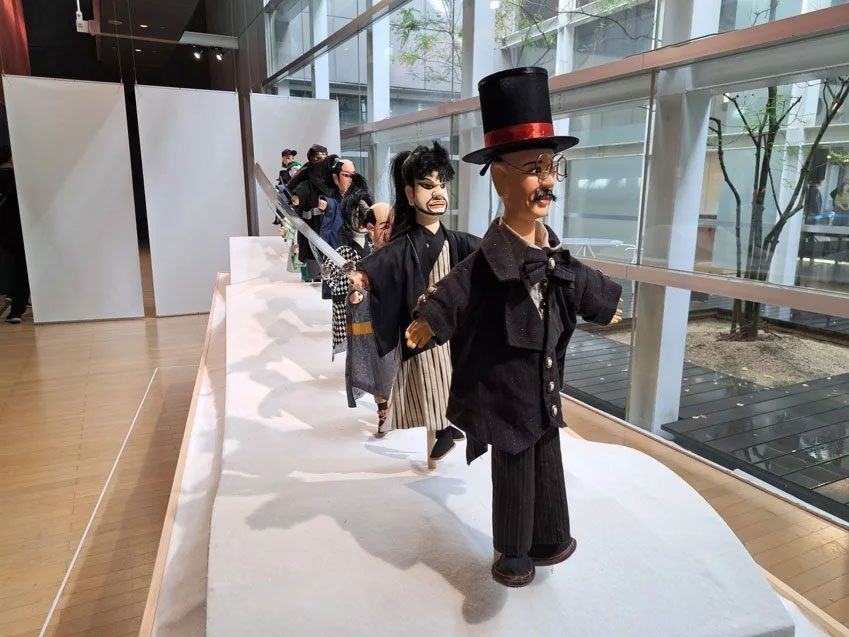〈移行期正義(Transitional Justice)〉……過去に大きな不正や人権侵害があった社会が、真実を追求して責任の所在を明確にすると共に、分断された社会の和解をめざし、より良い未来を築くために行なうプロセスのこと。
これまでの記事はこちら(連載:台湾・麗しの島〈ふぉるもさ〉だより)
東京中野区の小学校移転予定地に、「平和の門」と呼ばれる煉瓦造りの建築物がある。大正4年に建てられた旧豊多摩監獄表門(旧中野刑務所正門)のことで、かつて小林多喜二や大杉栄ら政治犯や思想犯が多く収監された。衛生環境は劣悪だったといい、哲学者の三木清はここで獄死している。近年、この門の保存をめぐって論争が起こっていたが、「文学や歴史など学問と深く結び付いている門で、戦争の社会的背景や平和の意味を学ぶために必要不可欠」という市民らの努力により、中野区の指定文化財として移築保存が決まった。市民運動に参加していた友人、現代中国研究者の阿古智子さんから経緯を聞いたが、関わった大人から子どもまで、地域の歴史や人権に多くの人が思いをめぐらせたようだった。こうしたプロセスは紛れもなく日本における「移行期正義」のひとつではないかと思う。
台湾では2017年に《移行期の正義促進条例》が施行され、過去の権威主義的な統治のもとなされた不当な人権侵害についての真相究明と名誉回復、加害者の責任究明、そして多様なアウトプットをもった人権教育が積極的に行なわれている。2018年には新北市にある「国家人権博物館 白色恐怖景美記念園区」が開館し、白色テロ被害者の口述や映像の記録、手紙、日記といった資料が公開されるほか、床上ぎりぎりの小さな窓から供された食事を「犬のように食べた」牢獄の再現など、受刑者の生活がいかに人としての尊厳を傷つけるものであったかを伺い知れる。
拷問と思想教育──蔡焜霖さんのこと
わたしがこの博物館を訪れたのは3年ほど前。案内してくださったのは蔡焜霖(さいこんりん)さんだ。蔡さんは1930年生まれで、植民地台湾の「日本人」として15歳までを過ごした。母語は台湾語と日本語で、終戦後は無実の政治犯として服役し10年の歳月を送った。刑期を終えたのち、日本語力を生かして広告代理店や出版社で奮闘、1960年代に雑誌『王子』を創刊して日本の漫画を台湾へ伝え、漫画文化を育んだ。お会いしたときの蔡さんはちょうど90歳だが、「あの」10年を振りかえる口調はまるで昨日起こった事を語るようだった。自分の経験を次の世代に伝えねばという使命感が、記憶を真空パックし、生き生きとさせている。
ことの起こりは、翌年の1950年9月10日。一党独裁のもと、1949年から国家の非常事態に発令される戒厳令が敷かれていた。戒厳令下では、「共産党スパイ」を捕まえるため、特務機関、軍関係者、憲兵、警察は「刑法100条」のもと疑わしい市民を逮捕して尋問や拷問にかけることができた。刑法100条とは、「国体の破壊、国土および憲法の不法な変更、政府転覆を意図し、企てた実行者は7年以上の懲役:首謀者は無期懲役。その予備犯は、6カ月以上5年以下の懲役に処する」というもので、「意図し、考えたり」「口にした」だけで恣意的に反乱罪に問える。そのため、台湾全土で数十万人以上が犠牲になったとも言われる。