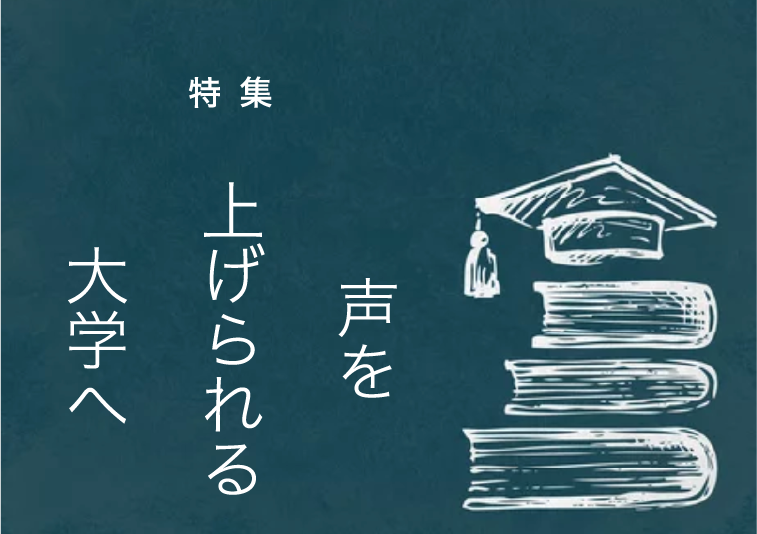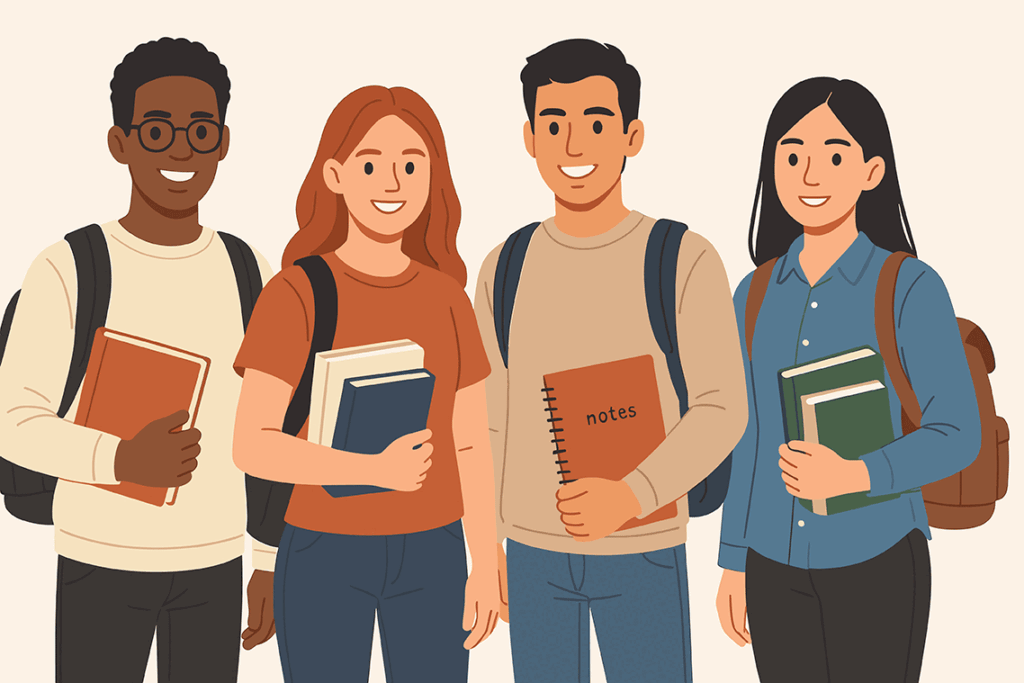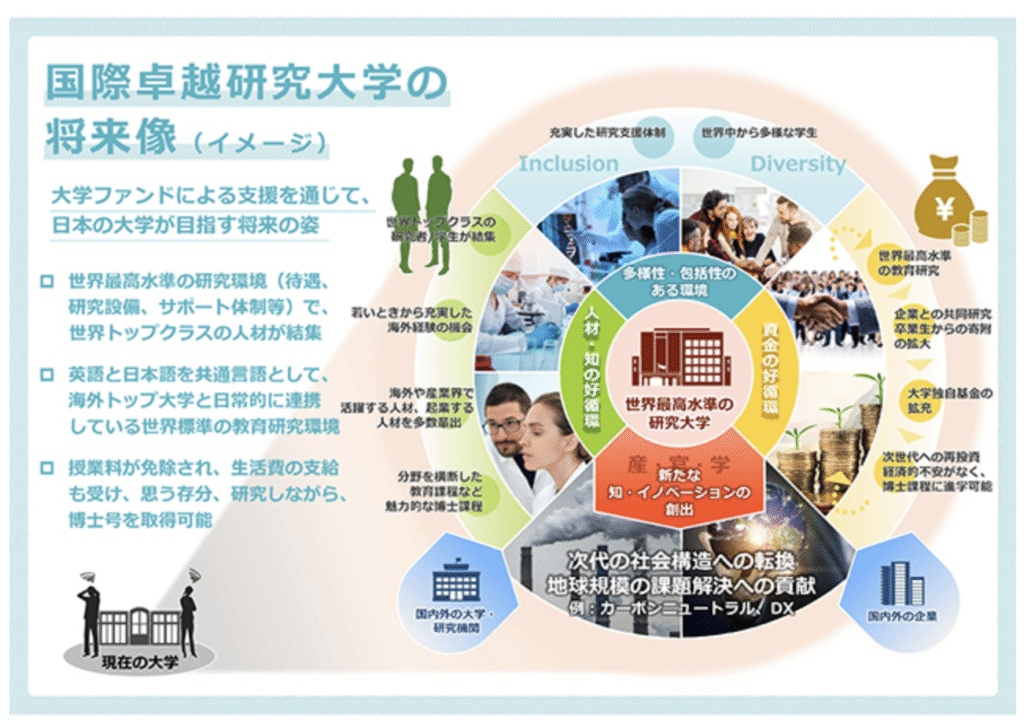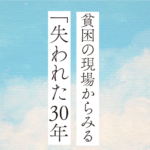学生は大学の「お客さん」ではない
広島大学 原田佳歩(はらだ・かほ)
「広島大学学費値上げ阻止緊急アクション」代表、「広島大学よりよいキャンパスライフを目指す会」代表
広島大学(広大)では、東京大学における学費値上げ方針が報じられてから約1週間後、学長の定例会見で授業料値上げの検討が明らかになりました。
「地方国立大学授業料値上げ第1号」となるのを阻止すべく、翌日には「学費値上げ阻止緊急アクション」を立ち上げ、活動を始めました。6月からは署名活動を展開し、1カ月あまりで1万7612筆を集めて学長に提出、事実上、値上げの検討を撤回させることができました。
学生も教員も知らないままの値上げ検討
学費が比較的安い地方国立大学は、経済的な事情を抱える人の受け皿となっています。地域に根差した大学として、より多様な人の学ぶ権利を守るうえで重要な役割を果たしています。広大の学費値上げ検討が教育格差の深刻化を招くのではないか、そして広大を皮切りに全国に学費値上げ検討が波及するのではないかという危機感を持って、活動に力を注いできました。
署名では学費値上げ検討に至ったプロセスの不透明性と、広島大学の最大の当事者である学生との対話が行なわれなかったことへの問題提起も盛り込みました。
授業料値上げについては2年前から検討されていたことが明らかになりました。それにもかかわらず、5月の学長定例記者会見で学長が口にするまで、学生・教職員は一切知らない状況でした。
学生を意思決定に参画させるべき
今回の値上げ報道以前から、学長選考規定・人事制度の改悪などが目立ち、トップダウンで決定されていく現在の大学運営に疑義を呈する声は多くありました。学費値上げの検討もその延長線上に位置付けられます。大学の独立性を取り戻すために、声をあげつづけていくことが重要だと考えています。
そして、大学の意思決定に学生が参画していけるように働きかけていくことが重要です。
学費値上げの問題に顕著ですが、大学における最大のステークホルダーは学生であるにもかかわらず、学生は重要な問題の決定について蚊帳の外に置かれている状況です。学生は大学の構成員ではなく「お客さん」とみなされ、コロナ禍以降は特に、一方的に学生生活規則を改定され、大学による学生の管理が強化されつづけています。
規則の改定により、大学内でのビラ配りや演説、立看板の設置を制限する条項、サークル活動を阻害する条項が盛り込まれ、学生の表現の自由はなくなりつつあります。このような状況に「おかしい」と声をあげつづけ、学生としての立場を鮮明にして、学生の権利を取り戻し、拡大していくことが必要です。そのような日々の地道な取り組みがあってこそ、学費値上げ反対運動のような大きなうねりが作り出せるのだと思います。
広島大学ではいったんはストップされましたが、まだ東大のように学費値上げが強行される可能性は残っており、注視が必要です。「学費値上げ阻止緊急アクション」として学費値上げ反対・高等教育無償化の必要性を訴えつつ、学内の諸問題にも目を向け、学生の権利向上のために活動していきたいと考えています。
学生による自主的な意思決定および管理=学生自治の再生のために今後も尽力していきます。
手探りしつつ声をあげる
熊本大学 関 立雄(せき・たつお)
熊本大学文学部4年。「学費増額に反対する熊大生有志の会」(肩書は当時)
2024年6月、熊本大学の小川久雄学長が、定例記者会見にて「授業料値上げ」に言及した。ちょうど東京大学で授業料値上げの検討が明らかにされ、学生からの激しい反対運動が起こった頃だった。いわく、「大学の財政状況が厳しい」という。危機感をおぼえた私はすぐに同級生に連絡し、有志の会を立ち上げた。
取り組みを開始
活動の経験もノウハウも持ち合わせていない私たちは、行動しようにも何をすればいいのかわからなかった。熊大には学生自治会がなく、学生が声を上げたいときにそれを組織としてバックアップする仕組みがない。学生同士で問題意識を共有し、議論することさえ難しいのが現状だ。
そこで私たちは、東大の「学費値上げ反対緊急アクション」など、協力を得られそうな組織に連絡をとり、アドバイスを受けた。有志の会でも話し合い、まずは値上げに対する私たちの懸念を学長宛てのメールで伝えることにした。
翌7月には東大本部が正式に値上げを決定するとささやかれる中、熊大本部もいつ値上げの本格的検討に入るかわからないという不安を抱いていた。東大が値上げを決定すれば、間違いなくその動きは全国に波及するからだ。
署名集めも考えたが、それにはやはり時間がかかる。まずは、「値上げへの不安」を学生が感じていることを大学当局に知ってもらおうと思い、学長宛てにメールを送った。東大や広大の学生が展開していたような大規模な運動ではない。だが私たちとしては、学生の権利を獲得していくための運動が少ない一地方で、右も左もわからないながらに、最初の「活動」を始めたのだった。
大学からの回答
数日後、大学本部から「現時点で値上げは検討していない」との回答を得た。さらに「熊本大学新聞」7月号に小川学長へのインタビュー記事が掲載され、学長自ら「具体的な値上げの検討はしていないが、今後の財政状況次第ではその可能性はある」と語られていた。
こうした大学本部の見解を前に、私たちはどう動くべきか、迷った。熊大の財政難の背景には、国からの運営費交付金の削減と「選択と集中」方式の予算配分がある。ある意味で学生と大学本部(教職員)は同根の問題に直面しており、大学に対して意見するだけでは不十分ではないかと思うようになったのだ。もちろん学生側が大学本部を慮り、主張を自粛する必要はない。ただ、運営費交付金の削減などは極めて政治的な問題であるため、国に対して直接訴える必要があると強く考えるようになった。2025年2月の院内集会は、そのための第一歩であった。
厳しい生活の実情
院内集会では、高い学費と不十分な支援制度に苦しむ熊大生の実例を取り上げ、地方学生の置かれている状況を訴えた。一人暮らしで生活費をまかなうのに苦労し、ガスを止められた友人もいれば、家賃の安い学生寮に入ったはいいものの、その家賃すらも滞納せざるをえなくなる学生もいる。国立大学学生の実像は、世間の抱くイメージ以上に厳しいものなのだ。
この学費値上げ反対運動は、まだ始まったばかり。学生の苦しい状況を今以上に広く世間に周知し、私たちの主張を理解してもらう必要がある。
そのためにはまず、私たち有志の会自身が、「学生/教職員」や「学生/一般市民」といったような垣根を越えて対話していくことから始める必要がある。対話をする中で、「どう声をあげたらいいのか分からない」「声をあげる勇気が出ない」という人たちと共に運動の方途を探り、少しずつ成果を上げていければと思っている。
地方の国立大学は最後の砦
静岡大学 匿名希望
静岡大学1年。
私が通う静岡大学では、現在、学費値上げの検討は行なわれていません。しかし、広島大学や熊本大学のようにある日突然、検討の俎上に載るかもしれないという危機感から、学費値上げに反対する運動に携わっています。
終わりの見えない物価高騰は、多くの大学生にとっても喫緊の課題となっています。一人暮らしの学生からは、電気やガスの高騰から暖房や風呂の使用を控えている、実家暮らしの学生からは、家計が厳しいからアルバイトを増やしてくれないかと頼まれているなどと、それぞれの窮状を耳にしています。
奨学金拡充は代替策にならない
各都道府県の国公立大学は、家庭事情によらず大学進学を実現したい多くの学生にとって、最後の砦としての機能を果たしています。経済的負担から地元の国立大にしか進学できない学生、親と縁を切る形で故郷から離れた地で学費を稼ぎながら通う学生など、様々な事情を抱えた学生に学びの門戸を開くことが国公立大学の使命となっています。
国立大学の学費値上げは、そのような学生の学びを困難な状況に追い込むことになります。学費値上げにあたって奨学金制度の拡充を進めるとの発言がなされていますが、東京大学では具体的な支援策が提示されないまま学費値上げの決定がなされており、それは批判を避けるための方便でしかないことが明らかになりました。
2020年度開始の就学支援新制度は6年目を迎えますが、その功罪が十分に議論されているとは思えません。院内集会では、世帯年収要件による経済DV被害者への無配慮、余暇時間や情報リソースに乏しい困窮学生が奨学金の申請をしなければならない「申請主義」、学業とアルバイトを両立させることの困難さ、教育現場を無視したGPA下位4分の1という学業要件などへの批判がなされました。このような問題点を解消しないまま形式的な奨学金拡充を行なっても、真に支援されるべき学生には届きません。
学生同士の連帯を再興させていく
学生運動の時代から半世紀、多くの大学では大学と学生の対話の場が失われており、学生を取りまとめる団体も存在しません。静岡大学では90年代に学生自治会や学生新聞が消滅し、学生が主体的に大学づくりに参画していくモデルは過去のものになっています。教育サービスの消費者という位置に固定化された学生に対して、来年度入学者からの学費値上げという、在籍する学生に直接かかわらない施策への反対に連帯してもらうことの困難さは、一大学生として痛感しています。全学的な反対運動を作り上げた皆さんに敬意を示しつつ、この動きをより大きく、政治をも動かす波にしていかなければならないと感じています。
現国会では私立高校の授業料について所得制限の撤廃が実現されようとしていますが、先んじて実質的に無償化を進めた維新の大阪で起きているのは、教育予算の削減や公立高校の定員割れ、統廃合です。予算審議で教育が議題の俎上に載る今だからこそ、聞こえの良いスローガンに踊らされることなく、教育予算拡充を訴えたいと思います。
私立大学の学費は高すぎる
中央大学 匿名希望
中央大学2年。「学費値上げに反対する中大生の会」
中央大学では2024年9月、中央大学生向けポータルサイト上において突如、2025年度からの学費値上げの計画が告知された。内容は、2025年度入学生から、授業料と施設整備費をそれぞれ毎年2%、約2~3万円ずつ値上げしていく、というものだ。
私たちは、学費値上げという重大な問題について、学生に広く周知されず、決定への参画も保障されないまま進められていることに危機感を持った。
圧倒的な反対
そこで、まずは値上げ計画があることを学生に広く知らせるとともに、計画に対する中大生の意見を集めて大学に届けようと、10月初旬にアンケートを実施した。結果は、学費値上げ計画の存在やその内容を知らなかったと回答した学生が9割以上にのぼった。値上げ計画への賛否では、「反対」が70%、「どちらかといえば反対」が19.1%で、約9割という圧倒的多数が反対の意思を示した。
主な反対の理由としては、「現行のままでも学費はとても高く、家計の負担、心理的負担もあまりにも大きい」、「高等教育は個人的利得ではなく公共性を有する。社会発展に寄与し還元されるべきもの。また、経済的理由で学問に十分取り組めない、進学をあきらめる若者を増やしてはならない」といった声があった。
学生の厳しい生活実態
実態についての調査では、3人に1人を超える学生が、金銭的事情から、興味関心のある進路選択を諦めた、もしくは不安であると回答している。
さらに、学生の健康に関わる「経済的理由から食事が偏ることや十分に取れないことがある・あった」という回答が20.4%あり、「経済的理由から病院に行くのを我慢あるいは躊躇することがある・あった」という回答も10.5%あった。今の学生はここまで追い詰められている。
私たちは昨年12月末、大学に対し、アンケート結果と、オンラインで寄せられた1万筆を超える署名とを提出し、学費値上げ撤回を求める要請を行なった。
大学側からは今年1月末日に書面で正式な回答があった。しかし、回答では大学財政の厳しさが縷々述べられている一方で、学生の置かれている厳しい生活実態については全体を通して一言も言及がなかった。
物価高騰もあって、大学側の経営が逼迫していることは事実だろう。しかし、それは学生も同じである。大学は、学生の生活実態、学びの困難な現実に目を向けるべきだ。もう生活がギリギリという学生は多くいる。これ以上、学生を苦しめないでほしい。
私立大学の高学費を下げていく
現在、日本の全大学生のうち約8割は私立の大学に通っており、日本の高等教育において不可欠な存在になっている。1975年に私立学校振興助成法が成立した際に、私立大学が果たしている社会的役割をふまえ、経常費補助を「できるだけ速やかに2分の1とするよう努めること」との付帯決議が採択された。現在では経常経費の約1割にまで抑えられている助成金を、国会決議に即して増やしていくことで、学費値上げを止めるだけでなく、あまりにも高すぎる現在の学費を下げていくことは可能だと考える。
私立大学と国立大学との学費との差を問題にし、その差を縮めるために国立大の学費を上げようという議論もあるが、学生の学ぶ権利を保障するうえでは私立も国立もどちらも値下げしていくことこそ必要だと強く訴えたい。
大学に通うということが特権である社会ではなく、だれもが豊かに学ぶことができる社会にするために、まずはその一歩として学費値上げを今すぐに止めることを強く望む。