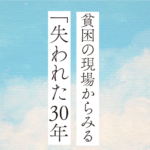1 協力医療機関を受診する患者が急増している
HPVワクチンについて、接種後の症状の治療のために国が指定した協力医療機関を受診する患者が急激に増えていることをご存じだろうか。
HPVワクチンは、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染を原因とする子宮頸がんを予防することを目的としたワクチンだ。「子宮頸がんワクチン」とも呼ばれる。2009年にサーバリックス(グラクソ・スミスクライン社)、2011年にガーダシル(MSD社)、2020年にシルガード9(MSD社)が日本で承認されている。
2013年4月に小学校6年から高校1年相当の女子を接種対象とする定期接種となったが、そのわずか2カ月後に接種の積極的勧奨が中止され、2022年4月に再開された。
積極的勧奨中止の期間中も、定期接種ワクチンであることに変わりはないから無償で接種は可能であったが、接種率は約1%になった。再開後は、厚生労働省によれば、2023年度の全国年間実施率が、1回目の接種で62.1%、2回目40.1%、3回目24.9%である。積極的勧奨再開から2024年上半期までに合計226万人が接種し、その約半数がキャッチアップ接種(積極的勧奨中止の期間中に定期接種を受けなかった1997年度から2008年度生まれの女性を対象とした公費接種)の対象者である。
国は各都道府県に1つ以上の協力医療機関を選定している。これは副反応が疑われる患者の診療のためである。このような定期接種ワクチンはHPVワクチンの他にはない。協力医療機関を受診する新規受診患者は、積極的勧奨中止期間中はほとんどいなかったが、再開後は2024年12月までに545人が新規に受診している。2022年度は137人、2023年度は146人であったのに対し、2024年度は12月までの9カ月で前年の2倍近い262人となっている。本年1月の厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会(以下「副反応部会」という)では、2024年9月から11月までの3カ月だけで新規患者が149人に上ったことについて「夏を過ぎて一気に増えてきた」と報告された。
HPVワクチンの接種後の症状は後述のように多様で、時間をおいて生じることもあり、ワクチンとの関連性に気づくまでに時間がかかるうえ、協力医療機関を受診するのは、他の医療機関で対応が難しかった場合である可能性が高いから、受診患者の増加は深刻に受け止める必要がある。
2 圧倒的な頻発──重篤副反応疑い報告
副反応の多様な症状は、激しい頭痛、全身の痛み、歩行障害、視覚や聴覚などの感覚障害、著しい倦怠感などから、簡単な計算ができない、自宅に戻る道がわからないなどの認知・学習の障害に及び、複数の症状が1人の人に重なって生じるという特徴をもつ。
発症の正確な頻度は調査が行なわれておらず不明である。しかし、厚生労働省の公表資料では、重篤な副反応疑い報告は1万人に5人(サーバリックスまたはガーダシル)~2人(シルガード9)である。その頻度を他の定期接種ワクチンと比較すると圧倒的に高く、例えばMR(麻疹・風疹)ワクチンとの比較では約10倍、副反応が多いとされるHibワクチンと比較しても約4倍である。副反応報告は医師による自発報告であり、報告されるものは氷山の一角と言われる。加えてHPVワクチンの副反応はワクチンとの関連性を把握しにくく、実際の頻度はもっと高いものと推測される。